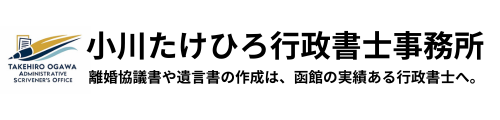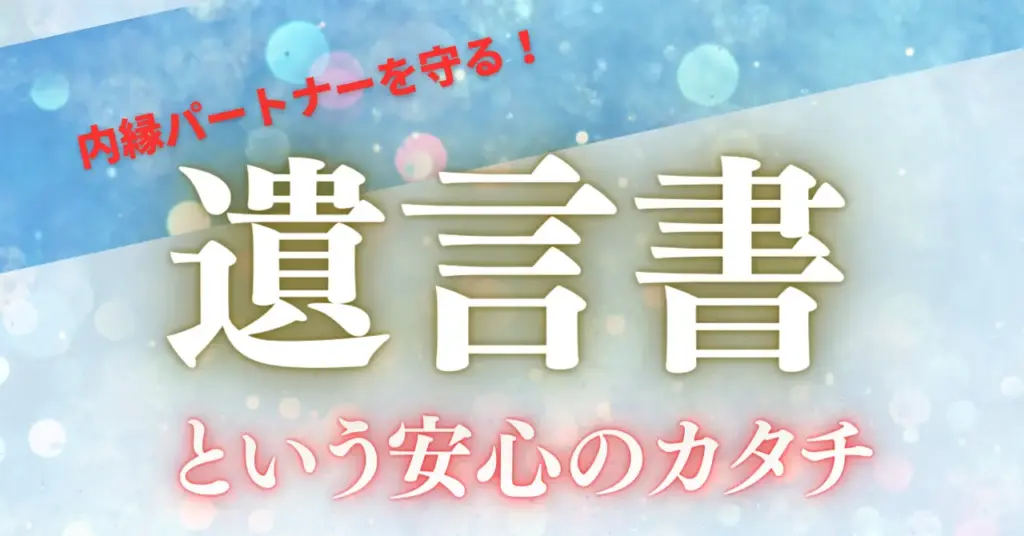“夫婦じゃなくても安心”を形にする「事実婚契約書」徹底ガイド

近年、法律婚にこだわらず、自分たちらしいパートナーシップを選ぶカップルが増えています。国勢調査によれば、事実婚や内縁関係を選ぶ人は年々増加傾向にあり、特に30代〜40代の層でその傾向が顕著です。 背景には、「結婚」という形に縛られず、柔軟な生き方を重視する価値観の変化があるでしょう。
しかし、事実婚は法律上の「配偶者」として認められないため、いざという時に困るリスクが潜んでいます。
- 急病時に「家族」として医療同意できない
- 内縁パートナーの死亡時に、相続権がない
- 財産分与や生活費分担でトラブルになる
つまり、「好きだから一緒にいる」だけでは守れない現実があるのです。では、これらのリスクからお互いを守るにはどうしたらいいのでしょうか?
【関連記事】
内縁関係でパートナーが亡くなったときの相続・遺言の備え方
内縁関係でパートナーが亡くなったときの相続・遺言の備え方 「結婚はしていないけれど、一緒に暮らして長い」という方は、今や珍しくありません。近年では、法的な婚姻関係を持たないまま、内縁(ないえん)関係を築くカップルも増えて […]
事実婚契約書とは? ~“ふたりのルール”を明文化する~
事実婚契約書とは、婚姻届を提出せずに共に生活するパートナー同士が、生活費、財産、医療、介護などの重要事項について、お互いの意思を文書で明確に取り決める契約書です。
単なる口約束では、第三者に対して証明できないため、万一のときに不利益を被る可能性があります。
事実婚契約書で取り決める代表的な内容は
- 生活費の分担方法
- 財産の管理・共有に関するルール
- 医療行為への同意、看護の希望
- 別れた場合の財産分与・慰謝料の取り決め
- 延命治療や介護方針に関する考え
これらをあらかじめ文書で取り決めておくことで、ふたりの生活基盤をより安定させることができます。
事実婚契約書で守れる大切な権利
ここからは、事実婚契約書によってどんなトラブルを防ぎ、どんな権利を守れるのかを具体的に見ていきましょう。
1. 生活費の分担ルール
事実婚カップルのトラブルで多いのが「家計の負担」の不公平感です。 家賃や生活費をどちらがどれくらい負担するのか、最初は曖昧でもうまくいっているように見えることがありますが、時間の経過とともに「自分ばかりが多く払っている」という不満が蓄積され、やがて深刻なすれ違いや感情的な対立につながることがあります。 また、外からは見えにくい金銭感覚や支出の優先度の違いが原因で、気づかぬうちに生活のストレスや相手に対する嫌悪感が高まることも少なくありません。
契約書では 、家賃・光熱費・食費といった主要な支出項目ごとに、どちらがどれだけ負担するのかを収入比率や役割分担に基づいて明確に定めます。たとえば「家賃は収入比で7:3、光熱費と食費は半々で」といった具体的な数値で合意することで、日常の家計管理がスムーズになり、不公平感も減ります。
さらに突発的支出(家電や車の故障、急な引越し、医療費など)が発生した際に、どうやって費用を分担するかをあらかじめ決めておくと安心です。特別費用用の共通口座を設けて毎月積み立てる方法なども取り入れると、将来に備えた安心感が生まれます。
2. 医療に関する同意・介護に関する希望
もしパートナーが突然倒れたら──。救急搬送された病院で、医師から治療方針について判断を求められたとき、法律上の配偶者でなければ、たとえ何年一緒に暮らしていたとしても「家族」として認められず、同意権が与えられないことがあります。 実際、内縁パートナーが医療現場で意見を聞き入れてもらえず、本人の希望と異なる処置がなされたケースが現実にあります。
契約書では 、 緊急手術・延命治療に対する希望を共有し、どちらが判断を下すのかを文書により明確に定めておくことで、万一のときに本人の意思を尊重した判断がされやすくなります。必要に応じて、任意後見契約や尊厳死宣言書、公正証書などとの併用も検討するとさらに確実です。
また、介護が必要になった場合の希望(たとえば在宅で過ごしたいのか、介護施設での生活を望むのか)や、経済的・精神的負担をどう分担するかも、あらかじめ具体的に話し合っておくと安心です。介護に関する役割分担や介護費用の支出方法まで定めておけば、将来の衝突や困惑を回避できます。
3. 財産管理・共有財産の保護
たとえばふたりで協力して購入したマイホームが、住宅ローンや契約上の都合で一方の名義になっていた場合、別れる際に「これは自分の名義だから出ていってほしい」と一方的に言われるリスクがあります。事実婚では法的な夫婦関係がないため、共有財産の法的主張が難しく、これまでの貢献が一切考慮されないということも起こりかねません。また、預貯金や有価証券、車や家具といった高額な動産も、名義が一方に集中しているとトラブルのもとになります。
契約書では 、 不動産については、名義が一方であっても共有で取得したことを認めた上で、持ち分割合や、売却時の配分方法、居住継続の条件などを細かく定めておくことが可能です。また、預貯金や証券類に関しても、どちらがどの程度管理するか、共有口座の使用条件などを記載しておくことで、後々の争いを避けることができます。
4. 別れた場合のトラブル防止
別れるときに揉める最大の原因は「お金」と「住まい」です。 長年連れ添ってきたふたりであっても、いざ関係を解消する場面では、感情が先走り、冷静な話し合いが難しくなることがよくあります。 とくに、財産の名義が一方に偏っていた場合や、どちらが住み続けるかの合意がない場合は、大きなトラブルに発展しがちです。 場合によっては、精神的なストレスから家庭裁判所での調停に至ることもあります。
契約書では 、 財産分与の基準、慰謝料の支払い有無、金額の目安、分割払いの方法など、具体的な内容を取り決めておくことができます。 また、別居する際の費用負担や引越し費用の分担、家の名義変更の要否、持ち家の売却有無など、現実的な生活設計まで合意しておくと、トラブルを未然に防げます。
冷静な合意をあらかじめ交わしておくことで、感情に流されることなく、落ち着いて別れのプロセスを進めることができます。後悔のない形での再出発を可能にするためにも、契約書による明文化は大きな意味を持ちます。
行政書士ができるサポートとは?
事実婚契約書はご自身で作成することも可能ですが、インターネット上のテンプレートを利用する場合などには、当人同士の状況や希望に適合していないケースも多く、内容に抜けや不備があると、いざというときに法的効力が十分に発揮されないリスクもあります。 文言の不備や法的根拠の曖昧さによって、病院や行政窓口で契約内容が受け入れられないケースも報告されています。
行政書士に依頼すれば
- ふたりの生活背景、収入状況、家族関係などを丁寧にヒアリングし、トラブルになりやすい部分を事前に把握します。
- 抜け漏れなく、ふたりの状況に合わせた有効な契約書をオーダーメイドで作成できます。
- 必要に応じて、公証役場との調整を含めた「公正証書化」までサポート可能。第三者にも確実に示せる形式で仕上げられます。
- 一度契約を交わしたあとでも、ライフスタイルの変化や家族構成の変更に応じて、契約内容の見直しや修正にも柔軟に対応します。
一度作った契約書が“終わり”ではなく、“これからの暮らしを支えるもの”として機能するよう、継続的なサポートも受けられる点は、専門家に依頼する大きなメリットのひとつです。
まとめ
事実婚を選んだふたりにとって、「事実婚契約書」は単なる書類ではありません。そこには、お互いの価値観や人生観、将来への思いやりが詰まっています。ふたりの信頼と愛情を、目に見えるカタチにする行為そのものが、事実婚における最大の安心につながります。
単なるリスク管理ではなく、
- 自分たちの暮らしを守る
- いざという時にお互いを守る
- 老後や介護といった将来への不安を減らす
- 万が一のときでも第三者にふたりの意思を正しく伝える そんな「見えない絆」を、文字という形で残しておくことができるのです。
「今は仲がいいから大丈夫」と感じていても、人生は予想できないことの連続です。急な病気や事故、仕事や収入の変化、家族との関係──どれも突然起こりうる現実です。
だからこそ、後悔しないために備えておくこと。
そして、それをふたりで考える時間そのものが、信頼を深める貴重なプロセスにもなります。
まずは一歩。堅苦しい手続きではなく、ふたりのこれからを守る“前向きな準備”として、話し合いから始めてみませんか?
小川たけひろ行政書士事務所では、 事実婚・内縁カップル向けに、個別事情に応じたオーダーメイド契約書作成をサポートしています。大切な人との未来を守るために、まずはお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付