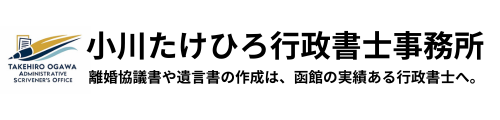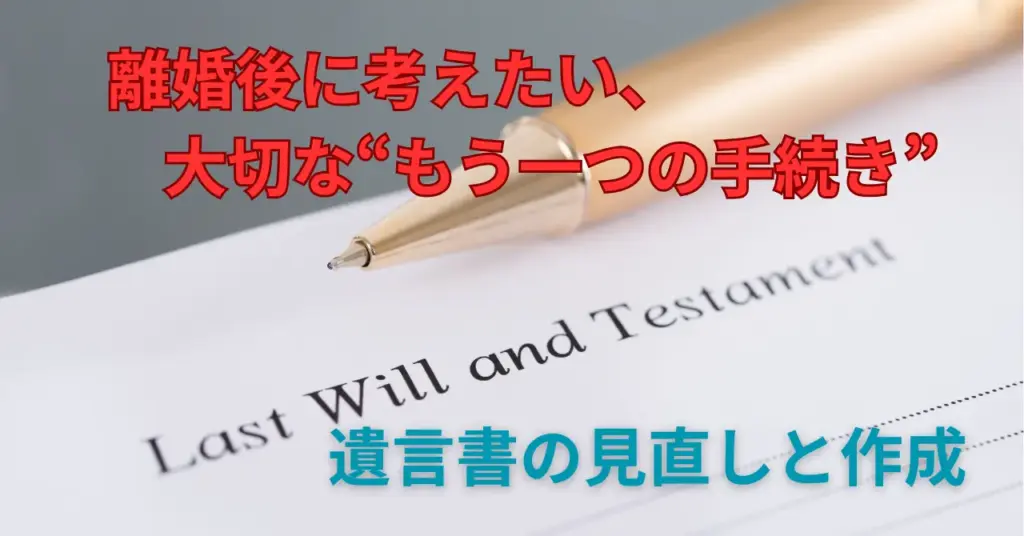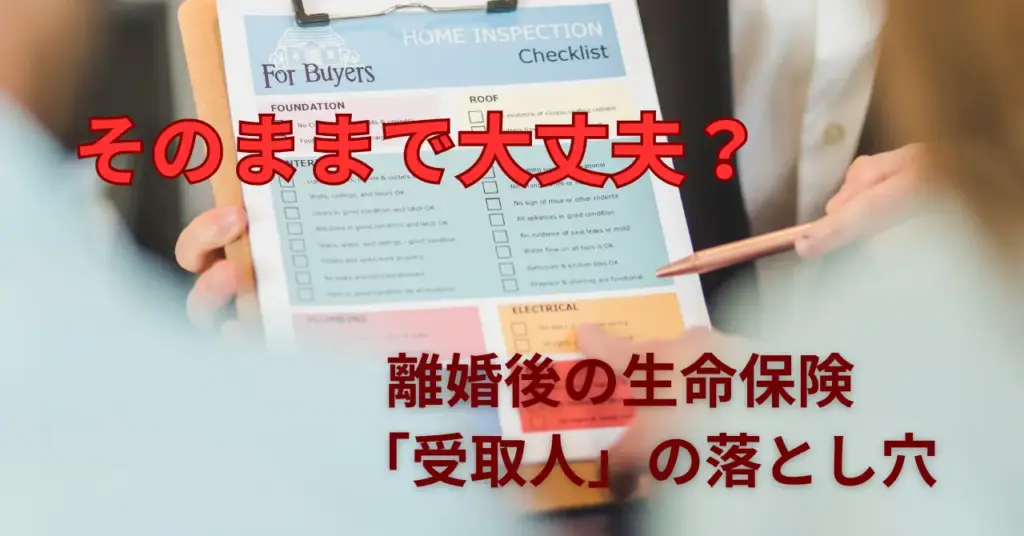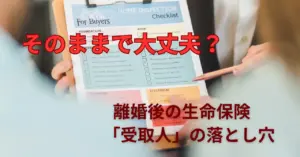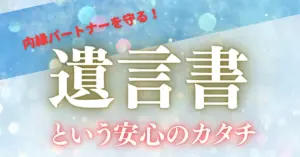離婚後、実家に戻る前に知っておきたい5つの注意点

離婚をきっかけに、「とりあえず実家に戻ろう」と考える方は少なくありません。 親との関係が良好であれば、住居や育児の面で大きな支えになることもあるでしょう。金銭的な負担が軽くなったり、家事や子育てに協力してもらえるなど、精神的にも助けられる場面が多くあります。
一方で、実家という場所は「安心できる避難所」であると同時に、「再出発の環境」として慎重な判断が求められる場でもあります。親世代との価値観の違いや、生活リズムのギャップ、兄弟姉妹との関係性など、暮らし始めて初めて気づく問題も少なくありません。
また、実家に戻ることで一時的に安心できたとしても、それが長期的な自立や子どもとの関係性にどのような影響を及ぼすかを冷静に見極める必要があります。感情に流されるだけでなく、「生活の再構築」という視点を持ち、現実的な備えをしておくことが重要です。
本記事では、離婚専門の行政書士としての立場から、実家に戻る前にぜひ知っておいていただきたい5つの注意点を、具体的なケースも交えながらお伝えします。
【関連記事】
離婚後の生活設計を考えている方には、以下の記事もおすすめです。
離婚と同時に考えたい「遺言書」の話 ―離婚後を安心して暮らすために―
離婚と同時に考えたい「遺言書」の話 ―離婚後を安心して暮らすために― 離婚が決まると、住まいの移動や名字の変更、財産分与、子どもの養育費の取り決めなど、短期間でさまざまな手続きが必要になります。生活を立て直すだけでも手い […]
離婚後の生命保険、受取人の見直しをしないまま放置していませんか?
離婚後の生命保険、受取人の見直しをしないまま放置していませんか? 離婚後の手続きには、引越しや住民票の異動、銀行口座の変更、子どもの手続きなど、目の前のことで精一杯になるものです。 その中で、生命保険の"受取人"について […]
住民票の移動は慎重に
離婚に伴って住民票を移す場合には、転出・転入届を出すタイミングに細心の注意が必要です。たとえば、夫婦間での協議がまだ十分に整っていない状態で先に住民票を移動してしまうと、「勝手に住所を変えられた」として感情的な対立やトラブルの原因となることがあります。
特に別居中の住民票移動は、養育費の負担割合や親権者・監護者の決定において不利になるリスクもあります。というのも、家庭裁判所などで親権を争う場合、実際に子どもと一緒にどこで生活していたのかが、親権者の適格性を判断するうえで重要な材料となるからです。
住民票が別の場所に移っていると、「実際には同居していない」とみなされるおそれがあり、相手側に有利に働くこともあります。また、住民票を移すことで、子どもを無断で移動させたと誤解され、連れ去りといった強い主張を受けるリスクも否定できません。
したがって、別居後の住民票移動は、慎重に検討し、できれば事前に相手と協議し、書面で合意を取っておくことが望ましいと言えます。
また、子どもの住民票についても、どちらの親と同一世帯にするのかは非常に重要な判断となります。進学や医療機関の手続き、児童手当の受給などにも影響を及ぼすため、十分な話し合いの上で、子どもの利益を第一に考えて決める必要があります。
実家に「お世話になる」という気持ちを忘れずに
「親子だから遠慮はいらない」という意識は、のちのち摩擦の原因になります。実家であっても、あくまで「一時的に住まわせてもらう」という意識を持つことが大切です。
家計の分担や生活費、光熱費の負担など、金銭面についても最初に話し合っておきましょう。住まいの提供だけでなく、食事や洗濯といった日常のサポートも受けることになるため、「どこまで頼るか、どこから自立するか」を明確にしておくことで、感謝と自立のバランスがとれた関係を築くことができます。
また、親の給料や年金に頼りきりでは、互いのストレスにもつながります。親の負担が重くなりすぎると、思わぬ衝突を起こしたり、自身が罪悪感を覚える場合もあるため、自分自身の生活設計と収支の見直しも必要です。
子どもの生活環境への配慮
実家に戻ることで、子どもの通学環境や交友関係が大きく変わる場合もあります。これまで慣れ親しんだ学校や友人と離れ、新たな環境に適応しなければならない状況は、特に年齢の低い子どもにとって大きなストレスとなることがあります。
転校のタイミングも慎重に検討する必要があります。学年の途中での転校は学習環境の変化だけでなく、人間関係の構築にも影響します。可能であれば、学期の切り替わりや進級のタイミングに合わせるなど、子どもの負担を最小限に抑える工夫が求められます。
また、祖父母との距離感も子どもの心理に大きな影響を与える要素です。温かい支援が得られる一方で、しつけや生活リズムの違いから戸惑いやストレスを感じることもあります。
さらに注意したいのが、祖父母が孫を過度に甘やかしてしまうケースです。とくに離婚というストレスを受けた子どもに対して、「かわいそうだから」として過剰に甘やかしたり、親が決めたルールを無視するような接し方をされると、子どものしつけや生活習慣に悪影響が出ることもあります。
親子関係と異なり、祖父母は「無条件の愛情」を注ぐ傾向が強いため、そのバランスが崩れると、子どもの自主性や自律心を育てる妨げになることもあります。必要であれば、祖父母とも話し合いを行い、育児方針について共有しておくと安心です。
子どもが安心して過ごせる環境を整えることを、何よりも優先して考えましょう。
親との生活習慣の違いに要注意
離婚によって精神的に疲弊しているなか、親との同居でストレスを感じる方も多くいます。特に、日頃の生活習慣や価値観の違いが表面化しやすく、思っていた以上に小さなことが気になり、気疲れしてしまうこともあります。
たとえば、食事の時間やテレビの音量、洗濯や掃除のタイミングなど、日常の些細な違いが積もり積もってストレスの原因になります。さらに、子育てに対する親からの口出しや、「昔はこうだった」といった押しつけ的な発言が繰り返されると、自己肯定感が下がったり、孤独感が強まったりすることもあります。
また、親自身も「良かれと思って」干渉してくることが多いため、直接的に意見を言いづらく、不満やストレスが蓄積しやすいという側面もあります。
そのため、一緒に暮らす期間を「一時的」と割り切ることで、心の余裕が保ちやすくなり、親との関係も悪化しにくくなります。できれば、自立へのステップとしての同居期間と考え、あらかじめ期限や目標を定めておくことが望ましいでしょう。
将来的な相続や居住権も視野に入れて考える
実家が親名義の家である場合、相続や居住権の問題が将来発生することもあります。たとえば、親が亡くなった後、その家を相続する際に、自分が継続して住み続ける権利があるのか、兄弟姉妹との間でどう分け合うのかといったことでトラブルになることがあります。
特に、他の兄弟姉妹が遠方に住んでいたり、家を売却して現金化したいと考えている場合、その家に既に住んでいる人の存在が大きな問題となることがあります。「住んでいるから退去できない」「売却に応じたくない」といった主張が対立を招き、結果として相続に関する協議が難航することもあります。
場合によっては、住んでいることが他の相続人にとって不公平に映ることもあり、これが火種となって感情的な衝突を引き起こすケースも少なくありません。相続人同士で感情的な対立が生まれやすく、関係性が悪化する原因にもなりかねないため、早めの話し合いが重要です。
こうしたトラブルを防ぐためにも、「今だけ住めればいい」という短期的な考えではなく、長期的な視点を持つことが大切です。親が元気なうちに、将来の相続や住まいについて、兄弟姉妹も交えた話し合いの場を設けておくことで、後々の混乱を未然に防ぐことができます。
行政書士の視点から見たアドバイス
実家に戻ることで、心身の安定や生活再建の足がかりが得られることも多くあります。特に、ひとり親となって経済的にも精神的にも不安定になりやすい時期に、家族の支援が受けられることは大きな助けになります。
しかしながら、そうした安心感に頼りすぎることで、将来的な自立や子どもとの関係性、家族内のバランスが崩れてしまうことも考えられます。そのため、感情や状況だけで判断せず、自分と子どもの今後の生活をどう設計していくのか、住宅・収入・子育て・老後との関係といった多角的な視点からの見直しが必要です。
また、実家の環境が現在のライフスタイルと合っているかどうかも重要なポイントです。家の間取りやプライバシーの確保、親の健康状態などを総合的に考慮し、自分と子どもが安心して暮らせる環境であるかを見極めることが求められます。
さらに、実家に戻って親や兄弟姉妹と生活を共にするなかで発生する金銭的負担の分担や、家事・育児・生活上のルールについても、後のトラブルを避けるために「口約束」ではなく、できる限り書面にしておくと良いかもしれません。簡単な合意書や覚書の形でも構いません。
なお、行政書士はこのような親族間での取り決めについて、文書の形式や内容が適切かつ法的に意味を持つように整え、当事者双方の意思が正確に反映されるようサポートすることが可能です。形式的な契約書というよりも、双方にとって理解しやすく、柔軟性のある穏やかな文書を作成するための支援を行います。
まとめ
「とりあえず実家に戻る」その選択が安心につながるか、それとも新たな問題の始まりとなるかは、事前の準備と心構えによって大きく左右されます。
実家との関係性、生活費の分担、子どもの教育や環境の変化、親との距離感、そして将来的な相続のことまで考えるべきことは多岐にわたります。一見すると頼れる「実家」という存在も、長く暮らすうえではさまざまな配慮が必要となるのです。
実家に戻ることで、家計や育児面での負担が軽減されるなどのメリットは確かにあります。しかしその反面、「感謝と自立のバランス」が崩れると、人間関係のトラブルや生活リズムのズレによってストレスを抱える原因にもなり得ます。
また、親や兄弟姉妹との価値観の違いが明るみに出ることで、かえって孤独感や疲労感が増してしまうケースも少なくありません。「戻ってよかった」と思えるためには、自分自身の生活設計を見直し、実家をあくまで“自立までの通過点”と位置づけることが大切です。
小さな違和感や我慢が積み重なる前に、現実的な視点での準備と家族との話し合いを大切にしましょう。 安心して新しい一歩を踏み出すために、「戻る」選択を前向きに活かす知識と行動を持つことが何よりも重要です。
離婚後の生活や実家への帰住にあたり、少しでも不安や迷いがある方は、まずは専門家にご相談ください。
小川たけひろ行政書士事務所では、離婚に関連する各種手続きや書類作成を通じて、実家に戻る方の再スタートを丁寧にサポートしています。暮らしを立て直す第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付