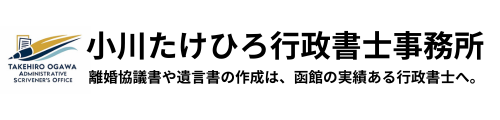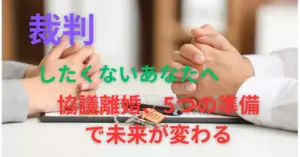離婚しないで、別々に暮らすという選択肢 メリットとデメリット

結婚生活において、必ずしも「一緒に暮らすこと」だけが夫婦のあり方ではありません。中には、さまざまな事情から離婚には踏み切らず、別々に暮らすという選択をする夫婦もいます。
その背景には、感情的な理由だけでなく、経済面・子どものこと・社会的な立場など、複雑に絡み合った要素が存在します。一見するとあいまいな関係に思われるかもしれませんが、それぞれにとって必要な距離や形を模索した結果の選択でもあるのです。
この記事では、ずっと別居状態で婚姻関係を継続することのメリット・デメリット、さらには後に離婚に至る場合の注意点について、現実的な視点から解説していきます。
別居と離婚ではどんな違いがあるの?
まず、長期間の別居をしながらも離婚をしない状態と、正式に離婚をした状態では、法律上や生活面でどのような違いがあるのかを整理しておきましょう。
相互扶助義務の有無
夫婦である限り、お互いを経済的にも支え合う義務(相互扶助義務)が法律で定められています。たとえ別々に暮らしていても、婚姻関係が継続している以上、この義務は変わることなく課せられています。そのため、収入の多い一方が、収入の少ない配偶者に対して生活費を補う形で支援を行う責任があるのです。
この義務のもと、たとえば子どもを育てている側が別居していたとしても、もう一方に生活費や養育に必要な費用の支援を請求することができます。実際に、調停や家庭裁判所を通じて「婚姻費用分担請求」として取り決めることも少なくありません。
一方で、離婚をすればこの相互扶助義務は法的に消滅し、以後はそれぞれが経済的に自立した存在として扱われることになります。そのため、離婚後は生活費(婚姻費用)を相手に請求することは原則としてできません。
公的支援の受給条件
たとえば「児童扶養手当」などのひとり親世帯向けの支援制度は、原則として法的に離婚が成立していることが受給の条件とされています。つまり、単なる別居状態では「ひとり親世帯」とは認定されず、制度の対象にはならないケースが一般的です。ただし、別居中でも例外的な事情がある場合には、受給が認められる可能性があります。
具体的には、配偶者からの暴力(DV)があった場合や、長期間にわたり子どもを養育していないなど、事実上の育児放棄(ネグレクト)が確認されたケースなどが該当します。このような状況にある方は、住んでいる自治体の福祉課などに相談し、事情を説明した上で支援制度の対象となるかを確認することが大切です。
役所によっては、状況に応じた証明書類の提出を求められる場合もありますが、制度の活用で経済的な負担が軽減されることもあるため、早めの相談が有効です。
税務上の扱い
税制面でも、婚姻関係を維持していることには一定のメリットがあります。たとえば「配偶者控除」や「配偶者特別控除」など、所得税や住民税の軽減につながる制度を活用できる可能性があります。これらは、配偶者の年収が一定以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要がありますが、世帯全体の税負担を軽減する上で大きな効果があります。
また、扶養に入っている配偶者がいる場合、健康保険の被扶養者として扱われることで保険料の負担を減らせることもあります。逆に、離婚をするとこれらの税制上・社会保険上の優遇措置は適用されなくなり、それぞれが個人として税や保険料を負担する必要が生じます。したがって、離婚による金銭的な影響は、単に生活費の問題だけでなく、こうした制度面でも生じることを念頭に置いておく必要があります。
相続権の有無
法律上の配偶者である限り、たとえ実際には長期間別居していたとしても、相手に対して法的な相続権が認められます。これは、同居・別居にかかわらず婚姻関係が継続している限り、法律上の「配偶者」としての地位が保たれているためです。
たとえば、別居中に配偶者が亡くなった場合でも、遺言書などで特別な指定がなければ、民法の規定に従い、配偶者としての法定相続分が認められます。加えて、相続税の配偶者控除など、法的な優遇措置も受けられる可能性があります。
一方で、正式に離婚が成立した場合は、その瞬間から配偶者ではなくなるため、当然ながら相続権も一切なくなります。この違いは、老後や万が一の備えを考えるうえで非常に大きな意味を持ちます。
離婚しないまま別居を続けるメリット
長年別居をしていても婚姻関係を維持することには、状況によっては思わぬ利点が見つかることもあります。たとえば、心身の距離を保つことで夫婦関係に新たなバランスが生まれたり、子どもの生活環境を急激に変えずに済んだりと、柔軟な対応ができる点が挙げられます。また、社会的な立場や経済的な背景を考慮して、離婚という決断を先送りしながら現実的に暮らしていくという方法も、選択肢のひとつとして注目されています。
このように、別居をしながらも法律上の夫婦関係を続けることで得られるメリットは、生活スタイルや家庭の状況によって多様に存在します。では、実際にどのような利点が考えられるのか、次に具体的な項目ごとに見ていきましょう。
関係を見直すための冷却期間ととらえることができる
顔を合わせるとケンカが絶えない、でも完全に縁を切るにはまだ踏ん切りがつかない──そんなとき、距離を置くことで関係が落ち着く場合もあります。お互いの存在が日常から離れることで、感情的な衝突が減り、冷静に相手の立場や自分の気持ちを見つめ直す時間が生まれるのです。
また、別居という形を取りながら時間を確保することで、過去の出来事や感情を整理し、関係の再構築に向けた準備期間として活用することも可能です。さらに、第三者(カウンセラーや専門家)のサポートを受けながら対話を重ねることで、誤解やすれ違いを少しずつ解消できるケースもあります。関係を断ち切るのではなく、一度立ち止まって「修復の可能性を見極める」ための時間として、別居という選択を前向きに捉える人も少なくありません。
子どもの気持ちに配慮できる
両親が離婚してしまうと、子どもが戸籍上や生活上で不安を感じることがあります。たとえば、名字が変わることによる周囲からの目や、家庭環境の大きな変化が精神的な負担となることも少なくありません。また、親権や面会の取り決めによっては、子どもが自由に両親と関わることが難しくなる場合もあります。
一方で、離婚せずに別居を選択することで、こうした環境の急激な変化を避けられる可能性があります。子の名字を変えずに済むだけでなく、形式的には両親が「一つの家族」であるという認識を保つことができ、心理的な安心材料となることもあるのです。
周囲の詮索や干渉を避けることができる
職業や家庭の事情から、離婚したことを周囲に知られたくないと考えるケースもあります。たとえば、公務員や教育関係者など、仕事上や地域社会での立場から「離婚」に対する目が気になることもあるでしょう。また、親族や子どもの学校生活への影響を心配して、離婚をためらう方も少なくありません。
そうした場合、あえて法的には婚姻関係を続けたまま、実際の生活は別々にすることで、余計な詮索や干渉を避けることができます。さらに、親族間のしがらみや資産・相続の問題から、戸籍上の夫婦関係を維持したほうが都合が良いと判断することもあります。このように、表向きの関係を保ちつつ、現実的には距離を置く「別居」という選択肢を取る方もいます。
婚姻費用の請求が可能
相手に収入があれば、別居中でも「婚姻費用」として生活費の支援を受けられる可能性があります。これは婚姻関係が続いていることによる法的な保護の一つです。婚姻費用には、生活費だけでなく、子どもの教育費や医療費なども含まれ、その範囲は思っているより広いのが実情です。
また、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所を通じて「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができ、一定の基準に基づいて金額が算出される仕組みがあります。こうした制度を活用することで、経済的に不安定になりがちな別居中の生活も、ある程度の安定を保つことが可能になります。
長期別居を続けることのデメリット
一方で、離婚をせずに長期間別居を続けることには、無視できないデメリットもいくつか存在します。一見すると、離婚という大きな決断を避けることで平穏に暮らせそうに思えるかもしれませんが、現実には思わぬ負担やトラブルの種が潜んでいることもあります。
精神的なストレスや経済的な負担に加え、法的な不利益を受けるリスクもあります。また、第三者が介在する新たな人間関係のもつれや、長期的な関係の不透明さによる不安など、日常生活において見えにくい問題が浮かび上がってくる可能性も否定できません。
さらに、時間の経過とともに、別居という状態が「中途半端な関係」として固定化されてしまい、今後の人生設計が曖昧なまま進んでしまうという懸念もあります。たとえば、老後の生活資金や介護の問題、再婚や相続に関するトラブルなど、将来を見据えた課題にもつながっていきます。
このように、別居という選択には冷静な判断と慎重な備えが必要です。では、実際にどのような不都合が生じ得るのか、以下に具体的なデメリットを項目ごとに見ていきましょう。
経済的負担が増える
生活の拠点が2つになるということは、それだけで家計の負担が増します。家賃や光熱費、水道代、インターネットなど、日々の暮らしに欠かせない固定費が二重に発生することになり、経済的な圧迫は避けられません。
さらに、日用品の購入や家電・家具などの生活環境を整えるための出費も、それぞれの拠点ごとに必要になります。特に子どもがいる家庭では、学用品や衣類、通学手段にかかる費用も倍増する可能性があります。別居生活が長引くほど、こうした費用は積み重なり、家計全体に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。
再婚ができない
婚姻関係が続いている限り、新たに好きな人ができたとしても、法律上は再婚することができません。つまり、現在の婚姻関係を解消しない限り、新しいパートナーと法的に夫婦になることは認められず、その関係は公的には「内縁」や「事実婚」として扱われることになります。
このような状況は、単に戸籍上の問題にとどまらず、相手との将来設計(たとえば子どもの認知、扶養関係、相続問題など)にも影響を及ぼします。また、新しいパートナーがいるにもかかわらず離婚が成立していない場合、周囲の理解を得にくかったり、パートナー側に心理的な負担をかけたりする可能性もあります。離婚をしていないという状態が、次の人生のステップを踏み出す上で大きな障害となることは少なくありません。
トラブルの火種になる可能性
別居期間が長くなると、相手から突然「離婚したい」と切り出されることがあります。これまで何となく現状維持で過ごしてきたつもりでも、相手側が心の中で決断を固めていた場合、唐突に話が進んでしまうリスクも否定できません。その際、調停や訴訟といった法的手続きに発展する可能性もあり、精神的な負担が一気に増すことになります。
特に、自分の中では関係修復の可能性を信じていた場合には、そのギャップから受けるショックは大きく、心の整理がつかないまま強制的に離婚の話し合いに進んでしまうケースも見られます。突然の展開に備えて、事前にある程度の心構えや情報収集をしておくことが大切です。
財産分与で不利になる可能性がある
長期別居をしていると、相手の財産状況を正確に把握することが難しくなります。別々に暮らしていることで、収入や支出の流れ、不動産や金融資産の管理状況を日常的に把握することができず、相手が資産を隠していたとしても気づきにくくなります。
また、離婚に向けて財産分与を行う際には、別居後に形成された財産は「共同で築いたものではない」と見なされ、対象外になるケースが多くあります。たとえば、別居後に片方が得た収入や購入した不動産、投資による資産の増加などは、財産分与の対象にならない可能性が高いのです。
こうした状況を避けるためにも、別居を開始する際にはその時点での資産状況を把握し記録しておくことや、可能であれば専門家の協力を得て調査や証拠の収集を進めておくことが重要です。これにより、後に離婚することになった場合でも、不利にならずに済む可能性が高まります。
不貞の証拠が得にくくなる
別居中に相手が不倫をしていたとしても、その証拠を掴むことは難しいケースが多く、慰謝料請求が難航する可能性もあります。実際に同居していれば、行動の不審点や不在時間などから気づきやすい場面もありますが、別居していると相手の生活の様子を直接把握する手段が限られてしまいます。
さらに、探偵を雇って証拠を集めるにも費用がかかり、精神的にも大きな負担となるため、途中で断念せざるを得ないケースも少なくありません。証拠がなければ慰謝料請求は認められにくく、裁判や調停で争う際にも不利な立場に置かれる可能性があります。そのため、別居期間中でも不貞の兆候に気づいた場合には、早い段階での証拠収集や法的アドバイスを受けることが重要です。
長期別居の後に離婚する際の注意点
最終的に離婚を選ぶことになったとき、それまでの別居期間中にどのような準備や行動をしてきたかによって、離婚後の生活に大きな差が生じることがあります。離婚では、財産をどう分けるか、子どもの親権や養育費をどうするかなど、重要なことを具体的に決めなければなりません。これらは感情だけで解決できるものではなく、法的な手続きや証拠も必要になるため、準備をしていないと損をしてしまう可能性があります。
特に気をつけたいのは、別居中に相手がどのような財産を持っていたのかをきちんと把握できているか、不貞行為があった場合にその証拠を持っているかなどです。これらの情報があいまいなまま離婚の話し合いに入ってしまうと、自分にとって不利な条件で合意してしまったり、必要な権利を主張できずに終わることがあります。
こうしたリスクを避けるためにも、別居中から計画的に情報を集めたり、記録を残しておいたりすることが大切です。具体的には、財産に関する書類のコピーを取っておく、不貞の兆候があれば証拠を確保しておく、日々のやり取りをメモに残すなどが有効です。
それでは次に、長期別居の末に離婚を決めた場合、どのような点に注意すべきか、具体的に見ていきましょう。
財産分与の対象期間が限られる
夫婦が協力して築いた財産は、基本的に財産分与の対象とされます。しかし、長期にわたる別居期間中に片方が得た収入や資産は、「夫婦として築いたもの」と見なされにくくなり、財産分与の対象から外れることが一般的です。たとえば、別居後に就職や転職をして収入が増えたり、副業や投資で得た利益、不動産や金融商品を購入した場合でも、それが夫婦の共同生活による成果と認められなければ、分与の対象にはならない可能性が高いのです。
このような不利益を避けるためには、別居を開始する時点での財産の状況を記録に残しておくことが重要です。預金通帳のコピーや不動産の登記情報、保険や証券口座の契約書など、具体的な証拠をあらかじめ確保しておくことで、後の交渉に有利に働くことがあります。特に、相手が資産を隠そうとしている場合や、収入状況が不透明な場合には、別居中であっても情報収集を怠らない姿勢が求められます。
慰謝料請求が難しくなることがある
夫婦関係がすでに破綻していたと判断されると、その後に相手が不貞行為をしても「慰謝料を請求できない」と見なされることがあります。裁判所では、関係が破綻した後の不倫には違法性がないと判断する傾向があるためです。
とくに別居期間が長くなると、夫婦関係がすでに終わっていたと受け取られやすくなり、不貞行為に対して慰謝料を請求しても認められにくくなることがあります。したがって、慰謝料請求を視野に入れる場合は、別居開始前後のやりとりや生活費の支払い記録など、「関係が破綻していなかった」と説明できる証拠をあらかじめ残しておくことが大切です。別居期間が長くなると、「破綻」と見なされる可能性が高まるため、不貞の慰謝料を請求したい場合は、別居前後の関係性や証拠の整理にも注意が必要です。
まとめ
離婚をせずに長期間別居を続けるという選択は、現代においてはもはや珍しいケースではなくなっています。夫婦のあり方が多様化する中で、必ずしも「同じ家で暮らす」ことだけが結婚生活の形ではないという考え方が広まりつつあります。別居を選ぶ理由には、感情のもつれやすれ違いを回避したいという心理的な側面だけでなく、家計の都合や子育て環境の安定、仕事上の事情など、さまざまな背景が絡んでいることが多いのです。そのため、他人から見れば不自然に思える状況であっても、当人たちにとっては納得のいく、現実的な解決策であることも少なくありません。
とはいえ、どんな選択にも良い面と悪い面があるように、長期別居にも多くの注意点が存在します。相互扶助義務や公的制度の適用範囲、税金や相続に関する法的な扱い、将来的に離婚を選択する際の準備やトラブルの可能性など、事前に理解しておくべきことは少なくありません。ただ気持ちのままに別居を続けるのではなく、今後の人生設計を冷静に見つめ直すことが、後悔のない選択につながります。
とくに、別居が長期化する場合は、「このままの状態で問題はないのか」「将来的に離婚という選択肢が現実的になったとき、どのような影響があるのか」といった疑問が浮かぶこともあるでしょう。そうしたときには、専門家に相談することで自分たちの状況を客観的に整理でき、新たな選択肢や対策が見えてくることもあります。法律や制度をうまく活用しながら、自分たちにとって最適なライフスタイルを見つけていくことが、これからの時代にはより重要になってくるのです。
長期間の別居を続けるか、それとも離婚という選択をするか。どちらの道にも迷いがあるものです。そんなときは、ひとりで抱え込まずに、気軽に専門家に相談してみませんか?
小川たけひろ行政書士事務所では、状況を整理し、お客様の手続き面での負担を軽くするお手伝いをしています。たとえば、離婚協議書の作成や公正証書の手配、財産分与や養育費などの取り決めも、必要な手続きをしっかりサポートいたします。
「今はまだ離婚までは考えていないけれど、不安はある」「このままの状態でいいのか確かめたい」――そんな気持ちにも丁寧に耳を傾け、あなたのペースで一緒に今後を考えていきます。モヤモヤした気持ちを少しでも軽くするためにも、お気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付