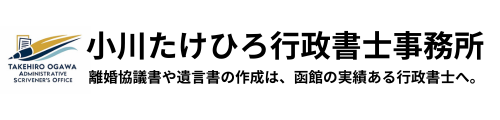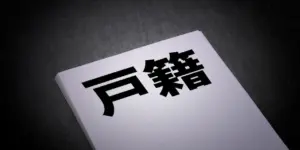離婚協議書について:メリット・デメリット、作成のポイントと記載事項(記載例付き)を解説

離婚協議書とは、離婚後に守るべき取り決め事項を文書にしたものです。
わざわざ離婚協議書を作らなくても私たちは約束を守るから大丈夫」と口約束だけで済ませて離婚してしまうご夫婦がいらっしゃいます。
たしかに、口約束でも有効に成立します。
しかし、口約束だけで済ませてしまうと、後々トラブルになることが多いのが現実です。
約束は守られなければなりません。
特に子どもがいる場合、養育費の確保は子どもの暮らしや成長に直結することであり、非常に大きな関心事になります。
そのためトラブルにならないよう必ず書面化しておくことが大切です。
この記事では、離婚協議書のメリット・デメリットや離婚協議書を作成するときに気をつけるべきポイントと代表的な記載事項を記載例付きで解説いたします。
- . 離婚協議書について:メリット・デメリット、作成のポイントと記載事項(記載例付き)を解説
- 1. 離婚協議書を作成するメリット
- 1.1. ①費用がかからない
- 1.2. ② トラブルになったとき証拠になる
- 1.3. ③ 取り決めたことを守ろうとする意識が働く
- 2. 離婚協議書のデメリット
- 2.1. ① 強制執行などのペナルティがないため約束が守られない危険がある
- 2.2. ② 内容の曖昧さがあるとトラブルを生み、法律的に無効な部分があると意味がなくなる
- 3. 離婚協議書の作成ポイント
- 3.1.1. 離婚協議書は、離婚届を出す前に作成する
- 3.1. 離婚後の再協議やトラブルを避けるため、漏れや曖昧さのない内容を目指す
- 4. 離婚協議書に記載する具体的な事項と記載例
- 4.1. 離婚に合意した旨の意思表示
- 4.2. 親権者
- 4.3. 養育費
- 4.4. 面会交流
- 4.5. 財産分与
- 4.6. 慰謝料
- 4.7. 年金分割
- 4.8. 通知義務
- 4.9. 禁止事項
- 4.10. 清算条項
- 5. 署名捺印して1通ずつ保有
- 6. 公正証書にしてより確実を目指しましょう
- 7. まとめ
離婚協議書を作成するメリット
離婚協議書を作成するおもなメリットは3つあります。
離婚協議書作成のメリット
① 費用がかからない
② トラブルになったとき証拠になる
③ 取り決めたことを守ろうとする意識が働く
①費用がかからない
夫婦が作る場合には費用はかかりません。行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると費用が発生します。
② トラブルになったとき証拠になる
取り決めを口約束だけで終わらせてしまうと後々トラブルになることがあります。
たとえば、「養育費は20歳まで」と取り決めたにもかかわらず、悪意のある相手が、「高校卒業までって約束したでしょう。」と主張すれば、必ず「言った、言わない」の水掛け論に発展します。
また、「月に一度、子どもに合わせる」という取り決めをして、離婚後、いざ面会交流しようと相手に連絡したとき「そんな約束した?」と言われれば、やはり水掛け論になってしまいます。
このように取り決めを口約束だけで済ませてしまうと、「言った、言わない」の水掛け論から深刻なトラブルに発展してしまうことがあります。
そのため、こういったトラブルを想定して離婚協議書を作成しておけば、取り決めたことが文字として残るため、いざトラブルになったときに「証拠」となります。
③ 取り決めたことを守ろうとする意識が働く
取り決めたことが文書として残っているため、「もし約束を破ったら、また相手と連絡を取り合ったり、最悪、調停や裁判になりそうで面倒だな」という意識が働き、約束を守ろうという意識につながる効果があります。
人にもよりますが、離婚協議という文書の存在は心理的に大きなプレッシャーになることは確かです。
離婚協議書のデメリット
離婚協議に関するデメリットはおもに2つが考えられます。
離婚協議書のデメリット
① 強制執行などのペナルティがないため約束が守られない危険がある
② 内容に曖昧さがあるとトラブルを生み、法律的に無効な部分があると意味がなくなる
① 強制執行などのペナルティがないため約束が守られない危険がある
離婚協議書を作っても、メリット③と逆の効果になる場合もあります。
「強制執行認諾条項付き公正証書」であれば、養育費や慰謝料が支払われなくなれば、相手の給料口座などを「差押え」して強制的に回収できる強力な効果を期待できますが、夫婦で作った離婚協議書にはこのような機能を付けることができません。
そのため、約束が守られないことがあります。
② 内容の曖昧さがあるとトラブルを生み、法律的に無効な部分があると意味がなくなる
せっかく離婚協議書を作ったのに、内容に曖昧な部分があったり、法律的に効力が生じない取り決めをした場合、離婚協議書を作った意味が失われてしまうことがあります。
たとえば、慰謝料100万円を10回の分割で支払うと約束したのに振込手数料はどちらが負担するのかという取り決めを曖昧にしていたためトラブルになることがあります。
また、「再婚は一切許さない」という取り決めをしても無効です。さらに、離婚協議書を作作成したときに離婚に合意していても、提出時に相手の気持ちが変わったような場合に、もう一方が勝手に離婚届を出してしまったような場合には、離婚は無効になってしまいます。
その結果、離婚することで効力を発する離婚協議書も意味をもたないことになってしまいます。
離婚協議書の作成ポイント
離婚協議書作成するときに、いくつか大事なポイントがあります。
離婚協議書は、離婚届を出す前に作成する
「一刻も早く離婚したい」「もう相手と話をしたくない」こういった気持ちが強く、大事な取り決めをしないまま離婚届を出してしまうご夫婦がいます。
しかし、離婚後、生活も落ち着き精神的にも冷静さが戻ってくると、養育費や財産分与、慰謝料など、取り決めしていないことを後悔することがあります。
離婚後でも取り決めすることはできますが、財産分与や慰謝料を請求するには期限があるので注意が必要です。
請求期限
- 財産分与 離婚成立から2年で請求権消滅
- 慰謝料 離婚成立から3年で請求権消滅
しかし、こういった請求期限については、注意していれば済むことですが、もっとも大きな懸念は「元配偶者と話し合う事が出来るのか?」ということです。
たとえば、夫が慰謝料を払わなければならない立場で離婚したなら、わざわざ自分にとって「支払い」というデメリットしかない離婚協議書を作成することに積極的に協力しようとは思わないでしょう。
また、いざ、離婚協議書を作成しようと、相手に連絡を取ろうとしたが、電話番号もアドレスも変わっていたり、職場や住所が変わっていて、連絡を取ることができなく可能性があります。
このような状況に陥らないためにも、離婚届の提出前に離婚協議書の作成をしておきましょう。
離婚後の再協議やトラブルを避けるため、漏れや曖昧さのない内容を目指す
離婚協議書の内容に漏れがあったり、内容に曖昧な部分があると、離婚後に再度話し合いをする必要があったり、解釈を巡ってトラブルになることがあります。
例えば、養育費について次のように離婚協議書に記載したとしましょう。
記載例は次のとおりです。
「第〇条 甲は養育費として、毎月3万円支払う」
この場合、「養育費について文書にしたから安心」と喜んではいられません。
なぜなら、内容が曖昧だからです。
この条項には、
・甲は誰に対して、養育費を支払うのか?
・どの子の養育費なのか(子どもが複数人要る場合)
・支払い方法は、現金なのか?振り込みなのか?
・振込の場合、手数料はどちらが負担するのか?
・支払いはいつから始めるのか?
・子が何歳になるまで支払うのか?
といった、誰が実行しても同じ結果になるために必要な内容が記載されていません。
これでは、いざ支払いとなったときに相手に確認しなければならなかったり、改めて話し合いをしなければならなかったり、最悪トラブルになってしまうかもしれません。
離婚後の再協議やトラブルを回避するためにも、漏れや誰が実行しても同じ結果になるような、曖昧さのない内容に仕上げる必要があります。
離婚協議書に記載する具体的な事項と記載例
離婚協議書には一般的に記載される事項があります。ここでは、離婚協議書に記載されることが多い事項について記載例を交えて紹介します。
記載例は、あくまで一般的な場合を想定して例示しております。
離婚に至る原因や事情によって、離婚協議書に盛り込まれる事項や記載の仕方に違いがあることがほんとんどです。
たとえば、マイホーム(住宅ローンを抱えている)などの不動産を所有しているご夫婦であれば、自宅のどうするのか、ローンは誰が支払うのか、どちらが住み続けるのか などを離婚協議書に盛り込む必要があります。
また、生命保険や学資保険などの扱いについても話し合って記載する必要があります。
そのため、一般的な記載例だけでは対処できないことも多く、そういった場合は、離婚協議書に詳しい行政書士や弁護士などの専門家に相談または作成依頼して、曖昧さや漏れのない離婚協議書を作成を目指すことをおすすめします。
離婚に合意した旨の意思表示
離婚するという意思を書面に表します。離婚意思のもとに取り決めをして離婚協議書を作成したという意思表示をします。
【記載例】
夫 ○○○○(以下「甲」という。)と妻 ●●●●(以下「乙」という。)は、令和〇年○○月○○日、協議離婚することに合意し、次条以下のとおり合意した。
夫婦のどちらが離婚届を提出するのかを記載する場合もあります。
親権者
親権者とは、子どもと同居して子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理する権利や義務を持っている者のことをいいます。
父母が結婚している間は、父母が共同で子どもの親権者となります。
しかし、父母が離婚する場合、現在の法律のもとでは「共同親権」は認められていないため、父母のいずれかが単独で親権者となります。
【記載例】
甲乙間の未成年の長男▲▲▲▲(平成●●年●月●日生、以下「丙」)、次男■■■■(令和●年●月●日生,以下「丁」)の親権者を乙と定め、乙において監護養育する。
養育費
養育費は子どもを育てるために必要な費用のことで、「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「交通費」「娯楽費」といった費用をいい、子どもが経時的に自立できるまで支払われます。
いざ、養育費の金額を取り決めしようとしても、養育費の相場がどのくらいなのか分からないことが多いと思います。
そのため、裁判所のホームページに養育費・婚姻費用算定表というものがありますので参考にすると良いでしょう。
しかし、算定表はあくまでも標準的なものであり、算定表の金額に縛られる必要はありません。あくまで、夫婦当事者の事情を考慮して取り決めましょう。
【記載例】
甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和●年●月から令和●●年●月(丙が満22歳に達した後に到来する3月)までの間、1カ月金〇万円の支払い義務のあることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
面会交流
離婚をすれば夫婦の関係は終了しますが、親子の関係は切れません。子どもと離れて暮らす親が子どもと交流をする権利を面会交流権といいます。
面会交流の内容や頻度については、父母が話し合って決めることになります。
面会交流で大事なことは、子どもの気持ちや状態を優先して考えてあげることです。
「会いたいから」とか「会わせたくないから」という親の一方的な気持ちで、無理強いしたり、拒否してはいけません。
【記載例】
乙は、甲が丙と面会交流することを認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は、子の利益を最も優先して考慮しながら、甲及び乙が協議の上これを定める。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に精算することをいいます。
原則2分のⅠずつ分割するのが原則ですが、夫婦の合意によって、この割合を変更することは可能です。
また、婚姻前からの財産、相続を受けた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。
「特有財産」を含めて財産分与をすると後悔します!
「特有財産」を含めて財産分与をすると後悔します! 婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚時に夫婦で分けることを財産分与といいます。 財産分与は婚姻期間中に夫婦が築いた共同で築いた財産を対象としますが、この中に、自己の財産で […]
【記載例】
甲は乙に対し、財産分与として金●●万円を令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。
2 振込み手数料は甲の負担とする。
慰謝料
配偶者から暴力を受けたり不倫をされ、精神的な苦痛を受け、離婚にいたった場合 配偶者や不貞行為の相手方(配偶者の不倫相手など)に対して請求できる金銭を慰謝料といいます。
慰謝料は必ずしも発生するものではなく、いつでも請求できるものではありません。
離婚の理由が「性格の不一致」である場合やすでに十分は補償を受け取っていたような場合には請求できないものとされています。
また十分な原因があっても、時効によって請求することができなっている場合もあります。
【記載例】
甲は,乙に対し,本件離婚による慰謝料として,金●●万円の支払義務があることを認め、これを令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。
2振込手数料は甲の負担とする。
年金分割
年金分割は、厚生年金について、婚姻期間中に収めた年金保険料の納付額を夫婦が共同で納付したものとして、納付額の多い方から他方に分割する制度をいいます。
よく誤解されるのですが、相手の年金を半分もらえる制度ではありません。
【記載例】
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意し、乙は、離婚届提出後●箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。 甲(昭和●●年●月●日生)(基礎年金番号 ●●-●●●●●●) 乙(昭和●●年●月●日生)(基礎年金番号●●-●●●●●● )
通知義務
養育費や面会交流を取り決した場合などは、離婚後も相手と連絡が取れる状態にしておくことが大切です。
甲は、住所、連絡先又は勤務先を変更したときには、速やかに乙に通知するものとし、乙は、住所、連絡先又は金融機関の預金口座又を変更したときには、速やかに甲に通知するものとする。
禁止事項
配偶者が離婚を拒否していたり、離婚を前向きにとらえていない場合、親や友人・知人その他周囲の人などに対して、一方の配偶者の悪口や根拠のない出鱈目などを直接喋ったり、SNSに書き込むなどして相手を傷つけてしまうことがあります。
こうした誹謗中傷は、不愉快なものであり、内容によっては、相手を精神的に追い込んでしまったり、名誉を毀損してしまうことがあります。
離婚後も、誹謗中傷にさらされ続ければ、新しい生活を軌道に乗せる前に心身に悪影響を及ぼしてしまう危険があります。
こういった心配を排除するために、誹謗中書を禁止する条項を記載することがあります。
また、離婚に至った経緯や婚姻期間中の出来事などをむやみに第三者に話したりSNSに書いたりすることでストレスを感じたり、第三者による新たな誹謗中傷につながる恐れもあるため、離婚に至った経緯や婚姻期間中の出来事などを他人に話したり、SNSへ書き込むことを禁止する条項を記載することがあります。
【記載例】
甲及び乙は、本件離婚成立後に、理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷してはならない。また、離婚に至った経緯や婚姻期間中のできごとを、むやみに、第三者に話したり、SNS等に書き込みしたりしてはならない。
清算条項
離婚後、しばらくしてから、取り決め内容や取り決めしなかったことを蒸し返されることがあります。
そのため、離婚協議書で取り決めしたこと以外に金銭的請求をしたり、その他一切の請求をしない旨を取り決めのうえ、記載しておきましょう。
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
署名捺印して1通ずつ保有
離婚協議書は2通作成しましょう。
そして、それぞれに各自署名捺印してそれぞれ1通を保有します。捺印に使用する印鑑は三文判でも構いませんが、当事務所では実印を押すことをおすすめしています。
その際、一緒に印鑑証明書を添付するようにお伝えしております。
実印を押したのだから、印鑑証明書まで必要ないのではと思われるかもしれません。
しかし、実印と印鑑証明書をセットで本人以外の者が所持することは通常ありません。
そのため、離婚協議書には実印を押していただき、あわせて印鑑証明書を添付することで、本人がこの離婚協議書の作成に関与したという信頼度が高まります。
印鑑証明書を取得するには手数料がかかるため、負担に思われるかもしれませんが、公正証書とは違い、第三者が関与しない夫婦だけで作られた離婚協議書だからこそ、実印での捺印と印鑑証明書を添付することで、離婚協議書に対する信頼度を高めることができるのです。
公正証書にしてより確実を目指しましょう
公正証書とは公正役場で作成する証書のことで、養育費や慰謝料の支払いを怠ると裁判の判決を経ることなく差押えなどができるのです。
それだけ強い書類になりますので作成に費用もかかりますし、時間もかかってしまいます。
それでも債権者側からすれば作成しておいたほうがメリットはあります。
まとめ
この記事では、離婚協議書に記載すべき事項の説明と記載例を解説いたしました。
この記事の記載例は一般的なものであり、すべてのご夫婦に当てはまるとは限りません。
離婚の背景には様々な要因や事情があり、それらを十分考慮し、離婚後の生活に不安が残らないよう、過不足のない離婚協議書を作成することが必要です。
当事務所では、離婚協議書に関するご相談や作成依頼を承っております。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付