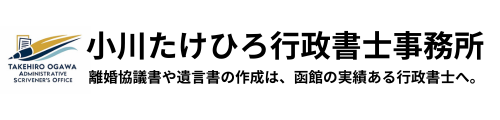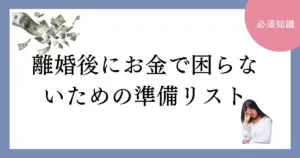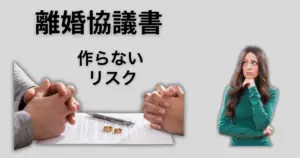離婚後の子どもの面会交流をスムーズにする方法

離婚後、別居親と子供の関係を維持するために重要なのが「面会交流」です。面会交流は、子どもの成長や心理的安定に大きな影響を与えるため、慎重に取り決める必要があります。
しかし、実際には面会交流の取り決めがうまくいかなかったり、感情的な対立やスケジュールの調整が上手くいかなかったりするケースも少なくありません。また、一方の親が面会を拒否する、子ども自身が面会を嫌がるなどの問題も発生する可能性があります。そのため、面会交流の具体的なルールを明確にし、準備を整えることが重要です。
この記事では、離婚後の子どもとの面会交流をスムーズに進めるための方法を詳しく解説し、適切な取り決めやトラブルを防ぐための対策について紹介します。
面会交流はなぜ必要?
面会交流は、子どもの健全な成長のために欠かせないものです。別居親と定期的に会うことで、子どもの心理的な安定を保ち、信頼関係を維持することができます。
面会交流のメリット
- 子どもが両親の愛情を感じられる
- 親子の関係を継続できる
- 子どもの精神的な安心感を確保できる
- 子どもの成長を見守ることができる
一方で、面会交流が適切に行われない場合、子どもの心に負担をかけてしまうことや嫌な思い出になってしまうこともあります。そのため、円滑な面会交流のために、事前にしっかりとルールを作っておくことが重要です。
面会交流をどう取り決める?
面会交流の取り決め方には、大きく分けて以下の3つの方法があります。
夫婦間の話し合いで決める
最も理想的なのは、夫婦間で冷静に話し合って面会交流のルールを決めることです。
話し合いで決めるポイント:
- 面会の頻度(月に何回か、週に何回かなど)
- 面会の場所(公園、親の自宅、レストランなど)
- 面会の時間帯と面会時間(昼間、夕方 2時間 半日など)
- 面会時の送迎方法(親が迎えに行くのか、子供を連れてくるのか)
- 連絡の手段(直接連絡するのか、間に第三者を介するのか)
- 泊りや旅行の可否(泊りや旅行はOKか)
離婚協議書や公正証書に明記する
離婚協議の際に、面会交流の取り決めを離婚協議書や公正証書に記載するのも良い方法です。これにより、後々のトラブルを防ぎ、確実に実行される可能性が高まります。
記載内容としては、具体的な日時や場所、送迎のルール、連絡手段などを明確にすることで、双方の誤解を避け、スムーズな面会が実現しやすくなります。こうした文書があることで、後々変更があった場合や追加の交渉が必要になった場合にも、スムーズに対応できるメリットがあります。
家庭裁判所の調停を利用する
話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の面会交流調停を利用することも可能です。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら適切な面会交流のルールを決めます。調停では、子どもにとって何が最善かを考え、具体的な取り決めを行います。
例えば、面会の頻度、場所、時間帯、送迎の方法など、細かな点についても話し合いが行われます。また、調停が成立しない場合には、家庭裁判所の審判により強制力のある決定が下されることもあります。
そのため、当事者が納得しやすい形での合意が期待できます。
面会交流をスムーズにするためのポイント
面会交流をスムーズに行うためにはどのようなことが必要なのでしょうか。
子どもの気持ちを最優先に考える
面会交流において一番優先されるべきは子どもの気持ちです。子どもが無理をしていないか、ストレスを感じていないかを常に確認しながら進めることが重要です。
子どもの意思を尊重しつつ、楽しい時間を過ごせるような工夫をすることが、面会交流の成功につながります。
ルールを守ることを徹底する
一度決めたルールを破ると、相手方との信頼関係が崩れてしまい、最悪、面会を拒否されてしまうこともあります。約束した面会の時間や場所を守り、トラブルを防ぎましょう。
感情的にならず冷静に対応する
元配偶者と顔を合わせる際に、感情的にならないように注意しましょう。子どもの前で争いが起こると、子どもの精神的な負担になります。
第三者を介する方法を検討する
どうしても直接やりとりが難しい場合は、親族や第三者機関である「面会交流センター」などに頼むことも選択肢の一つです。
第三者の介入方法
- 親族に付き添ってもらう
- 面会交流支援センターを利用する
面会交流支援センター 面会ネット
面会ネットは日程調整支援はもちろん、事前面談不要で付添い支援、引渡し支援などの面会交流支援を行っています。対象地区は全国の面会交流
面会交流が難しい場合の対応
状況によっては、面会交流がスムーズに進まないこともあります。以下のような場合には、適切な対処が必要です。
同居親が面会を拒否する場合
子どもと同居する親に面会を拒否された場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。調停では、双方の意見を公平に聞き、子どもにとって何が最善かを最優先に考えた面会交流のルールを策定することが目的となります。
調停委員が仲介し、日程や回数、連絡手段など具体的な取り決めを進めることで、合意形成を目指します。また、調停が不成立の場合には、家庭裁判所が最終的な判断を下す審判手続きを行い、適切な面会交流の条件を決定することが可能です。これにより、より拘束力のある取り決めがなされます。
子どもが会いたがらない場合
子どもが面会を拒否する場合、その理由を慎重に聞くことが大切です。子どもが面会を嫌がる背景には、両親の不仲によるストレス、新しい環境への適応、別居親に対する不信感など様々な要因がある可能性があります。
そのため、無理に面会を強制するのではなく、子どもの気持ちを尊重しながら無理させず進めていくことを考えましょう。例えば、最初は短時間のビデオ通話から始める、可能なら面会時に同居親が同席する、子どもの好きな場所で会うなど、段階的に関係を築いていく工夫が必要です。
面会時にトラブルが発生する場合
面会時にトラブルが発生する場合は、具体的な対処方法を事前に考えておくことが重要です。面会の際に子どもが不安を感じたり、一方の親がルールを守らなかったりするケースもあります。
こうした問題を防ぐために、面会交流の際には、スムーズに進めるための準備を整え、トラブルが起きた際の対応策を明確にしておく必要があります。
まとめ
面会交流は、子どもの健全な成長にとって極めて重要なものです。面会交流を通じて、子どもは両親の愛情を感じることができ、同時に心理的な安定を保つことができます。しかし、親同士の関係が悪化している場合、面会交流をスムーズに進めるのが難しくなることも少なくありません。
特に、感情的なしこりが残っている場合、面会交流の仕方で対立することもあります。そのため、面会交流のルールを明確にし、子どもの気持ちを最優先に考えながら進めることが大切です。
面会交流の場面では、子どもが安心して親と過ごせる環境を整えることが求められます。例えば、子どもが面会交流を楽しみにできるよう、無理のないスケジュールを組むことが重要です。また、親同士の接触や対話を極力減らしたい場合には、第三者を交えた引き渡し方法を検討することも効果的です。
また、トラブルを避けるための対策として、面会交流の取り決めを協議書や公正証書に残す、第三者を介する、家庭裁判所の調停を利用するといった方法を活用しましょう。
面会交流が子どもにとって安心できる時間になるよう、親としてできる最善の対応を心がけましょう。
小川たけひろ行政書士事務所では、離婚全般についてのお悩み相談や離婚協議書の作成、離婚公正証書作成サポートを承っております。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付