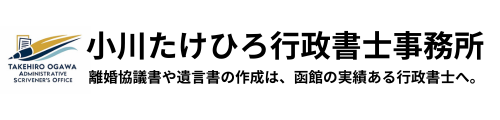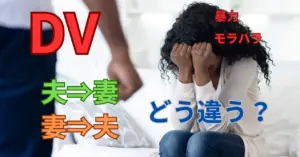養育費の支払い義務者または請求者が死亡したらどうなる?

養育費は、子どもが成長するために必要な費用であり、親の経済的な支援として重要な役割を果たします。しかし、支払いをする側(支払い義務者)や、受け取る側(支払い請求者)が亡くなった場合、この支払いはどうなるのでしょうか?本記事では、これらのケースについて説明していきます。
養育費の支払い義務者(支払う側)が死亡した場合
支払い義務は相続されない
養育費とは、子どもの成長に必要な費用ですが、それを支払う義務がある人(支払い義務者)が亡くなった場合、その支払い義務は相続人には引き継がれません(民法第896条)。
民法第896条(相続の一般効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
これは、養育費の支払い義務が個人的なものであり、一般的な財産とは異なるためです。たとえば、亡くなった人の預貯金や不動産は相続の対象になりますが、養育費の支払い義務は個人が負った義務であり、本人が亡くなった時点で消滅します。そのため、相続人が新たに養育費を負担する義務はありません。
未払い養育費は相続の対象になる可能性あり
しかし、すでに確定している未払いの養育費(たとえば、裁判の判決や公正証書によって支払いが義務付けられていたが、支払われていなかったもの)がある場合、それは亡くなった人の負債(借金)として扱われます。
そのため、相続人が、その負債を引き継ぐ可能性があります。つまり、相続人が遺産をそのまま引き継ぐ(単純承認する)場合は、未払いの養育費も含めて支払う責任が生じることがあります。
遺族年金・生命保険の活用
相続財産の中に未払いの養育費が含まれている場合、それを請求できる可能性はありますが、支払い義務自体は死亡とともに消滅します。また、未払い養育費の一部を相続財産から支払ってもらえることはありますが、あくまで、未払いだった部分ついてのみ請求できるだけで、相続人が、将来的に支払いを続ける義務があるわけではありません。
そのため、支払い義務者が死亡した後の養育費の確保が大きな課題になります。この問題に対応するためには、以下の制度を活用することが有効です。
遺族年金の受給
国民年金や厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、遺族が受け取ることができる年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類です。
養育費を受け取る子どもは、「生計を維持されていた」「子どもが18歳に達した年度の3月31日を経過していない」などの条件が揃えば、年金を受け取ることができます。ただし、受給できるかどうかは、亡くなった親がどの年金制度に加入していたか、どれくらいの期間年金を支払っていたかなどによって異なります。また、養育費の支払い義務者が再婚して、子どもがいいた場合には、その子との間で支給に関する調整が行われます。
遺族年金を受け取るには、決められた手続きを行う必要があります。具体的には、市区町村の年金窓口や日本年金機構に申請し、必要な書類を提出することが求められます。申請時には、死亡診断書や戸籍謄本、亡くなった親の年金記録などが必要になるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
遺族年金は細かい条件があり複雑なため、詳しく知りたい場合は、日本年金機構の公式サイト(こちら)やお近くの年金事務所などに相談することをおすすめします。
生命保険の活用
支払い義務者が生命保険に加入し、その受取人を子どもに設定している場合、養育費の代わりとして保険金を活用することができます。この場合、生命保険の保険金は通常、相続財産とは区別され、他の相続人と分ける必要がなく、受取人である子どもが直接受け取ることができます。
また、生命保険の契約内容によっては、保険金を一括で受け取るだけでなく、毎月決まった金額を分割して受け取ることも可能です。これにより、養育費と同じように定期的な収入として活用することができるため、子どもが生活していくうえで、安定的なサポートを受けることができます。
生命保険を活用する際には、契約内容をしっかり確認し、どのような形で保険金が支払われるのかを把握しておくことが大切です。また、保険の種類や受け取り方法によっては、税金がかかる場合があるため、事前に専門家に相談することも有効です。
養育費の請求者(受け取る側)が死亡した場合
養育費の支払い義務は継続する
養育費を受け取る側が亡くなった場合でも、養育費は子どものための費用であり、権利であるため、その権利が消滅することはありません。親が亡くなっても、子ども自身の生活費としての養育費を受け取る権利は維持されます。
まとめ
養育費を支払う義務がある人が亡くなった場合、その支払い義務は基本的に相続されません。しかし、生前に支払われなかった養育費がある場合、請求できる可能性があります。
また、養育費の支払い義務者が亡くなった後、子どもの生活費を確保する方法として、遺族年金や生命保険があります。遺族年金は、特定の条件を満たせば子どもが受け取ることができ、生活費を補う助けになります。一方、生命保険を活用すれば、相続財産とは別に保険金を受け取ることができるため、養育費のように継続的なサポートを受けることができるものもあります。
保険や年金制度を理解し、適切な対策をとることで、子どもが安心して生活できる環境を維持することができます。
また、養育費の請求者が亡くなった場合でも、養育費の支払い義務は変わらず継続します。
養育費に関する問題は状況によって異なるため、専門家に相談しながら適切な手続きを行うことが大切です。小川たけひろ行政書士事務所では、養育費についてのご相談、離婚協議書、離婚公正証書作成のサポートを承っております。
【関連記事】
養育費増額のリアルな本音とトラブル防止策
養育費増額のリアルな本音とトラブル防止策 離婚後に取り決めた養育費。けれど、子どもの成長や生活環境の変化によって「この金額では足りない…」と感じることも少なくありません。そこで検討されるのが「養育費の増額請求」です。しか […]
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付