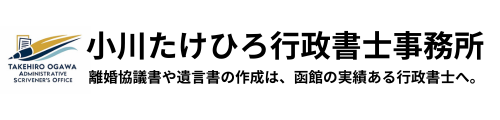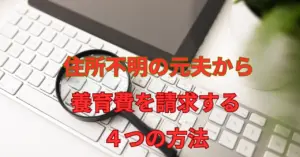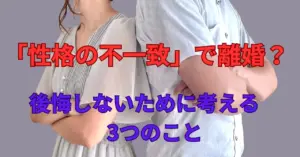離婚でペットと別れる…でも会いたい!面会の取り決め方法とポイント

ペットは家族同然の存在。しかし、離婚時にどちらが引き取るかで争いになるケースは少なくありません。そして、ペットを手放さざるを得なかった側にとって「もう二度と会えないのか?」という不安がつきまといます。
法律上、ペットは「物(動産)」とみなされ、子どものような親権や面会交流の制度はありません。しかし、元夫婦が合意すれば、離婚後もペットと会うことは可能です。本記事では、離婚後にペットと会うための具体的な方法とポイントを解説します。
離婚後にペットと会うことは可能なのか?
結論から言えば、双方の合意があればペットと会うことは可能です。しかし、法律上の義務がないため、合意がなければ面会を強制することはできません。
ペットと会うためのポイント:
- 離婚協議の段階で面会について話し合う
- 口約束ではなく書面で取り決める
- 円満な関係を維持し、元配偶者の協力を得る
- 面会時のルールを具体的に決めておく
- トラブル防止のために第三者を介することも考慮
- ペットの健康状態に応じた特別な対応を検討する
- できるだけペットに負担の少ない方法を選ぶ
離婚時にしっかりと取り決めをしておかないと、後から「やっぱり会わせたくない」と言われてしまうリスクがあるため、早めの対策が必要です。特に、ペットが病気になった場合や高齢になった場合の対応についても話し合っておくとよいでしょう。
また、面会を継続的に実施するためには、相手との関係を円満に保つことが重要です。無理に要求しすぎると逆効果になり、関係が悪化してしまう可能性もあります。ペットの幸せを第一に考え、お互いに納得できるルールを構築することが大切です。
ペットが不安を感じる可能性もあるため、頻繁に環境を変えることがないよう配慮し、面会時のストレスを最小限に抑える工夫も求められます。
離婚後にペットと会うためにするべきこと
① 離婚協議書や公正証書に明記する
ペットの面会を確実にするためには、口約束ではなく書面に残すことが重要です。
記載すべき内容:
- 面会の頻度(例:月1回、週末のみなど)
- 面会の場所(相手の自宅、ペットカフェ、公園など)
- 費用負担(交通費、飼育費の一部負担など)
- 急な体調不良時の連絡義務(病気やけがをした場合の報告)
- 面会に関するトラブル発生時の対処法
- 面会時間の長さと調整のルール
- 面会に関する第三者の関与(親族や友人を通じた管理)
これらを離婚協議書や公正証書に記載し、合意を得ることで、後々のトラブルを防げます。
② 面会時のルールを明確にする
ペットとの面会がスムーズに行われるためには、公正証書で取り決めた大枠のルールの他に、さらに細かいルールを決めておくとよいでしょう。
具体例:
- 毎月第1日曜日の午後1時~3時まで面会OK
- 事前に連絡を取り、都合が悪い場合は別日を調整
- 面会時のエサやおやつの持ち込み可否
- 面会時の写真・動画の撮影可否
- 面会時の連絡手段(電話、メール、LINEなど)
- 面会場所の安全性や適切な環境の確保
- ペットがストレスを感じないよう、会う場所を固定する
- 面会頻度の調整(年齢や健康状態に応じて変更可能)
お互いの負担を減らし、円満な面会を実現するために、細かい部分まで取り決めておくことが大切です。特に、ペットがストレスを感じないような環境で面会を行うことが理想です。
事例紹介
離婚後にペットとの面会を継続することは決して簡単ではありませんが、適切な取り決めや交渉次第で可能となります。ここでは、実際にペットと会うことができた事例を紹介し、それぞれのポイントを解説します。
ケース① 「公正証書で面会のルールを定めた夫婦」
Aさん夫妻は、離婚時に月1回の面会を公正証書に明記しました。具体的には、毎月第2土曜日の午後に、近所の公園で1時間面会することを取り決めています。また、面会時の連絡手段やペットの体調に応じたスケジュール変更のルールも詳細に記載し、どちらか一方の都合で一方的に面会が中止されることがないようにしました。
ポイント
- 公正証書に明記することで、面会の確実性を確保
- 面会の頻度・時間・場所を具体的に決めたことで、トラブルを回避
- ペットの体調や天候に合わせた柔軟な対応ルールを設定
このように、公正証書を作成することで、離婚後も安定した面会を続けることが可能になります。
ケース② 「養育費の一部を負担することで面会を実現」
Bさんは、離婚後にペットを手放すことになりましたが、「飼育費の一部を負担する」ことを条件に、毎月1回の面会を認めてもらいました。元配偶者にとっても、飼育費の負担が軽減されるため、この提案を受け入れることに合意しました。面会場所はペットカフェとし、ペットの健康管理やストレス軽減の観点から、同じ場所での面会を継続するルールを設定しました。
ポイント
- 飼育費の一部負担を交渉材料にし、面会の合意を得る
- 面会場所を固定することで、ペットのストレスを軽減
- 定期的な見直しを行い、負担が増えすぎないよう調整
このように、金銭的なサポートを申し出ることで、面会の可能性を高めることができます。
ケース③ 「第三者を介して面会を実現」
Cさんは、元配偶者と直接交渉することが難しく、ペットとの面会を諦めかけていました。しかし、共通の友人を仲介役として立て、間接的に交渉を進めることで、面会の機会を得ることができました。最終的には、ペットが通っている動物病院での定期検診の際にCさんも立ち会う形で、月に1回の面会を実施することになりました。
ポイント
- 共通の知人を介して交渉を進めることで、スムーズな合意を実現
- 動物病院での面会にすることで、ペットの健康管理も兼ねる
- 直接対面を避けることで、元配偶者との無用なトラブルを防ぐ
このように、第三者の協力を得ることで、面会の実現がスムーズになるケースもあります。
まとめ
離婚後も大切なペットと会いたい場合、まずは双方の合意を取り付け、書面に残すことが重要です。離婚協議書や公正証書に面会の条件を明記することで、後々のトラブルを防ぐことができます。具体的には、面会の頻度、場所、時間、費用負担の有無などを取り決めておくとよいでしょう。
また、面会時のルールを細かく決めることも大切です。例えば、ペットに対してどのような接し方をするのか、写真や動画の撮影が可能か、第三者を同席させるかなど、事前に合意しておくことで、スムーズな面会が実現します。さらに、ペットの健康状態や年齢に応じて面会の頻度を調整する柔軟性も必要です。
取り決め内容に不安がある場合には行政書士などの専門家のサポートを受けることも選択肢の一つです。法的に面会を確約するために公正証書を作成することで、より確実な合意が得られます。また、ペットのストレスを最小限に抑えるため、移動負担の少ない環境を選ぶ、オンライン面会を取り入れるなどの工夫も考えられます。
最終的には、ペットの幸福を第一に考え、双方が納得できる形で面会を続けることが理想です。円満な関係を維持しながら、適切な取り決めを行い、愛するペットとの時間を確保しましょう。
小川たけひろ行政書士事務所では、離婚に関する悩み相談、離婚協議書や離婚公正証書の作成サポートなどを承っております。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付