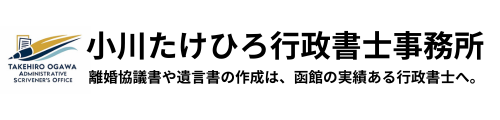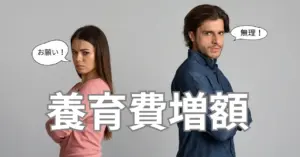夫と妻のDVの違いとは?男女差によるDVの特徴と対処法

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫婦や恋人間で発生する暴力のことを指します。一般的には「夫が妻に暴力を振るう」というイメージが強いですが、近年では「妻が夫に対してDVを行う」ケースも増加しています。しかし、性別によってDVの特徴や社会的な受け止め方には違いがあり、対応策も異なる場合があります。
この記事では、夫から妻へのDVと、妻から夫へのDVの違いに焦点を当て、それぞれの特徴や対処法を解説します。
夫から妻へのDVの特徴
身体的暴力の割合が高い
夫からのDVは、殴る・蹴る・突き飛ばすなどの身体的暴力が中心となることが多いです。力の差があるため、被害者である妻が大怪我を負ったり、最悪の場合、命に関わるケースもあります。また、暴力が繰り返されることで被害者の恐怖心が増大し、DVから抜け出せなくなる「支配の連鎖」が生まれることもあります。
さらに、身体的な暴力だけでなく、物を投げつける、壁を殴って怖がらせる、大きな音を立てて威嚇するなどの行為もDVに含まれます。特に、妊娠中や子どもが生まれたばかりの時期は、女性が疲れやすく不安になりやすいので、暴力を受けるリスクが高まるとされています。このような状況では、夫のDVがさらにエスカレートすることもあると報告されています。
こうした身体的DVの被害を受けた際は、すぐに医療機関で診察してもらい診断書を取得し、証拠を確保することが重要です。また、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談したり、シェルターの利用など、早急に安全な環境を確保するための具体的な行動を取ることが求められます。
支配的なモラハラも多い
夫が妻に対して、長期的にモラハラ(精神的虐待)を行うケースもあります。たとえば、「お前は何もできない」「誰もお前の言うことは信じない」といった暴言を繰り返したり、経済的に支配してお金を自由に使えないようにするなどの行為が見られます。
また、家族や友人との連絡を制限したり、外出を禁止することで、社会的な孤立を強要するケースも少なくありません。さらに、妻が自分の意見を言うと怒り出す、話し合いを拒否する、または無視することで精神的に追い詰めるパターンもあります。
こうしたモラハラは時間とともにエスカレートする傾向があり、被害者が「自分が悪いのかもしれない」と思い込んでしまう場合もあります。そのため、DVの証拠を記録し、信頼できる第三者や配偶者暴力相談支援センターに相談することが大切です。自分が現在置かれている状況を話し、適切なカウンセリングを受けることで、自分の状況を客観的に理解し、解決のための第一歩を踏み出す手助けになるでしょう。
社会的な認識と支援体制が整っている
夫によるDVは、社会的に問題視されやすく、女性向けのDV相談窓口やシェルターが多く設置されています。多くの自治体では、女性がDV被害に遭った際に迅速に保護を受けられる制度を整えており、特に子どもがいる場合には、安全な環境を確保するための支援が手厚くなっています。また、警察や行政機関も対応しやすく、通報を受けた場合には加害者への警告や保護命令の発令が行われることがあり、被害者が保護されるケースが比較的多いです。
さらに、法律の整備も進んでおり、DV防止法の改正により、保護命令の適用範囲が広がったり、被害者の証言が重視されるようになっています。また、女性支援団体による相談会や、被害者が社会復帰を目指すための支援プログラムも多く存在し、心のケアや就労支援なども行われています。このように、社会的にDV問題が認識され、被害者が支援を受けやすい環境が整えられています。
【相談窓口】
| 窓 口 | 対応内容・連絡先 |
| DV相談ナビ | 「どこに相談すればよいのかわからない」といった方は#8008に電話をするとお近くの「配偶者暴力相談支援センター」につながります。 詳しくはこちら |
| 配偶者暴力相談支援センター | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等を図るため、 相談や相談機関の紹介 カウンセリング 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※) 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助 を行います。 詳しくはこちら |
| DV相談 +(プラス) | 専門の相談員が対応 365日相談対応 電話・メール24時間受付 チャット相談12:00~22:00 電話 0120-279-889 詳しくはこちら |
| よりそいホットライン | 24時間無料で相談を受けている電話相談窓口電話番号:0120-279-338 詳しくはこちら |
妻から夫へのDVの特徴
モラハラが中心となる
妻から夫へのDVでは、殴る・蹴るといった身体的暴力よりも、**精神的な暴力(モラハラ)**が中心となるケースが多く見られます。例えば、夫に対して「役立たず」「給料が低い」「男として価値がない」などの暴言を繰り返すことで、夫の自尊心を傷つけ、心理的に支配しようとします。
また、無視をしたり、家事や育児のやり方を過度に批判したりすることで、夫に罪悪感を植え付け、コントロールするケースもあります。こうした精神的DVは長期間続くことで、夫が自信を失い、抑うつ状態になったり、仕事に悪影響を及ぼすことがあります。
身体的暴力が見られることも
一般的に、男性の方が体力的に優位であるため、妻から夫へのDVは身体的暴力の割合が少ないと言われます。しかし、次のような暴力が行われることもあります。
- 物を投げつける。
- 夫を引っかく、つねる、髪を引っ張る。
- 夫が寝ている間に暴力を振るう。
- 包丁などの凶器を持ち出して脅す。
特に、妻が強いストレスを抱えている場合、感情のコントロールができず突発的に暴力を振るうケースもあります。
子どもを使ったDV
妻がDVの手段として、子どもを巻き込むケースもあります。
- 夫の悪口を子どもに吹き込む(「お父さんはダメな人間」など)。
- 夫が子どもと関わることを禁止する。
- 夫が子どもの前で罵倒される。
このような子どもを使ったDVは、子どもに大きな心理的負担や与え、家庭内の関係性をさらに悪化させることに繋がってしまいます。
社会的な認識が低く、相談しづらい
夫が妻からDVを受けていても、「男なのに情けない」「妻にやられるなんて嘘だろ?」と周囲から理解されにくい問題があります。男性がDVの被害を訴えると、誤解されたり、深刻な問題として受け取られにくいことが多いです。そのため、被害者である夫が相談をためらい、問題が長期化するケースが少なくありません。
また、相談窓口も女性向けが多く、男性が安心して相談できる場が限られているのが現状です。ただ、多くの相談窓口では男性も対象ととなっているものがほとんどであり、男性のDV被害についても安心して相談できる体制が整っています。上記の【相談窓口】でご相談ください。
DVを受けた場合の対処法
証拠を確保する
DVを受けている場合、証拠を残すことが最も重要です。
- 身体的暴力: ケガの写真を撮影、病院で診断書をもらう。
- 精神的暴力: 録音、LINEやメールのやり取りを保存する。
- 物理的損害: 壊された物の写真を撮る。
専門機関に相談する
性別を問わずDV被害に対応している相談窓口を利用しましょう。
- DV相談ナビ(#8008):全国共通のDV相談窓口(24時間対応)。専門の相談員が対応し、適切な機関やシェルターを案内してくれます。
- DV相談ナビ +(プラス):専門の相談員が対応 365日相談対応 電話・メール24時間受付 チャット相談12:00~22:00 電話 0120-279-889
- 配偶者暴力相談支援センター:各地域に設置されている相談窓口で、シェルターの紹介や法律相談のサポートを受けられます。また、一時的な避難場所の提供や心理的ケアのサポートも行っています。
- 民間支援団体・NPO法人:男性のDV被害者向けの支援を行っている団体も増えており、専門的なカウンセリングやサポートを提供しています。
- 警察(110番):緊急性が高い場合に通報すれば、加害者からの保護や、接近禁止命令の手続きが可能になる場合があります。
安全を確保する(別居も視野に)
DVがエスカレートする可能性がある場合、安全を確保するために別居を検討しましょう。実家や知人宅、場合によってはシェルターを利用するのもひとつの方法です。特に、DVが継続的に発生している場合は、早急に避難することが重要です。
別居の際は、事前に滞在先を確保し、信頼できる家族や友人に相談しておくことが望ましいです。シェルターは女性専用が多いですが、最近では男性向けのシェルターも増えています。また、役所や自治体の支援窓口に相談すると、適切な避難先を紹介してもらえることもあります。
別居を決断する前に、できるだけ証拠を確保しておくことが重要です。DVの証拠(録音・録画・診断書・警察への相談記録など)があると、離婚調停や裁判で有利になります。さらに、別居後に生活費の確保が必要な場合は、婚姻費用分担請求を検討することも一つの方法です。
また、DV加害者との接触を避けるために、住所変更の手続きや電話番号の変更など、安全対策も考えましょう。DVがエスカレートするリスクを最小限に抑え、安心して生活できる環境を整えることが大切です。
DVを理由に離婚できるか?
DVは離婚を認めてもらう十分な理由になります。法律では、配偶者からの暴力が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される場合、裁判所が離婚を認めることができます(民法770条1項5号)。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
DVを理由に離婚する手順
1 証拠を確保する
医師の診断書(怪我の記録)を入手、警察への相談履歴(被害届・相談記録)、DVの録音や映像、破壊された物の写真
2 別居を検討する
DVが続いている場合、加害者と物理的な距離を取ることが重要です。
シェルターや信頼できる家族・友人の家に避難する。
3 離婚の手続きを進める
DV被害者は、話し合いによる離婚(協議離婚)が難しい場合が多いため、家庭裁判所に調停を申し立てることが一般的。
調停でも解決しない場合、裁判離婚となります。DVでの慰謝料は高額になる傾向があり50万円~300万円が相場になっています。ただ、被害程度によってさらに高額になる場合もあります。
DVによる離婚の場合、慰謝料の他に、以下のお金を請求できる可能性があります。
養育費:子どもがいる夫婦の場合、親権者となる親は、一方の親に対し、子どもが経済的に自立するまでの期間、養育費の支払いを求めることができます。
財産分与:婚姻期間中に夫婦が2人で築き上げた財産の分配を求めることができます。原則1/2ずつ分けるのが原則です。
婚姻費用:離婚が成立するまでの間、離れて暮らしていた場合、その間に発生した生活費の支払いを求めることができます。
DVを理由に離婚する際は、証拠を確実に確保し、支援機関などに相談しながら慎重に進めることが大切です。
まとめ
DVは性別に関係なく深刻な問題であり、迅速な対処が必要です。DVの被害を受けている場合、何よりもまず証拠を確保することが重要です。写真や診断書、録音データなど、DVの実態を示す証拠があることで、警察や裁判所、支援機関に相談しやすくなります。
また、DVの被害者が抱える心理的負担も大きく、恐怖心や恥ずかしさから誰にも相談できずにいる人も少なくありません。しかし、DVは一人で解決できる問題ではなく、信頼できる人や専門機関に相談することが解決の第一歩となります。自治体のDV相談窓口や民間の支援団体では、専門の相談員が対応し、安全な避難場所や法的な手続きをサポートしてくれるケースもあります。
さらに、DVから逃れるためには安全な環境の確保が必要です。特に身体的な暴力がエスカレートしている場合は、速やかに別居を検討し、シェルターや親族の家など、安全な避難先を確保することが大切です。また、DVの加害者からの報復を防ぐためにも、警察や配偶者暴力相談支援センター等の協力を得て保護命令を申請することも一つの方法です。
そして、DVが改善される見込みがない場合や、精神的・身体的負担が大きすぎる場合は、離婚も選択肢の一つとして考えるべきです。日本の法律では、DVは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められるケースが多いです。DVの証拠を確保した上で、専門家や専門機関に相談し、適切な手続きを進めることで、より安全で安心できる生活を取り戻すことができます。
何よりも重要なのは、一人で抱え込まず、勇気を持って行動を起こすことです。DVの被害を受け続けることは決して耐えるべきことではなく、被害者が安心して暮らせる環境を作ることが最優先です。周囲の支援を受けながら、自分自身の安全と未来のために、一歩ずつ前進していきましょう。
小川たけひろ行政書士事務所では、DVに関するカウンセリング、離婚についてのご相談を承っております。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付