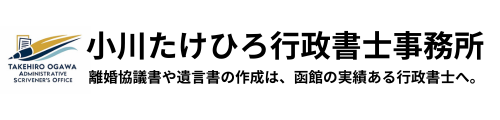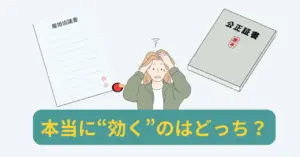プレゼントや指輪は返すべき?離婚・破局後の正しい判断の基準

離婚や破局の場面で、こんな言葉を投げかけられたことはありませんか?
「今まであげたプレゼント、全部返してよ」
「そのバッグ、俺が買ったんだよね?」
突然そんなことを言われて、戸惑ったり、モヤモヤした気持ちになったりした方もいると思います。
「いやいや、それって“あげた物”じゃないの?」
「返さないといけないのかな…でもなんだか納得いかない」
今回は、そんな“別れ際のモノの返還問題”について、法律的な正解と、そこに潜む人間心理をお話します。
法律上「贈与されたもの」は原則、返す必要なし
民法では、プレゼントや金品のやり取りは「贈与」として扱われます。
具体的には、民法第549条に次のように定められています。
(贈与)民法第549条
贈与は、当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって、その効力を生ずる。
つまり、プレゼントを渡した時点で贈与契約が成立し、原則としてあとから「やっぱり返して」とは言えないことになります。
また、仮にその贈与が書面によらず、口頭やLINEなどでなされたものであったとしても、すでに渡してしまった(=履行が完了している)場合は撤回できません。
(書面によらない贈与の撤回)民法第550条
書面によらない贈与は、その履行が終わっていない部分については、各当事者がこれを撤回することができる。
つまり、「まだ渡していない分」については口頭でも撤回可能ですが、「すでに渡したプレゼント」については書面がなくても原則として返してもらえないということです。
返す必要が出てくるケースも一部あり
とはいえ、例外も存在します。
- 条件付きの贈与(婚約指輪など)
「結婚すること」を前提に贈られた場合、結婚が破談になれば返す義務が生じることがあります。 - 忘恩行為(ぼうおんこうい)があった場合
たとえば、詐欺的にモノを受け取ったような場合や、著しい裏切り行為があった場合などには、贈与を取り消せる可能性があります。
ただし、こうした例外はかなり特殊なケース。通常のプレゼントについては、「もらったものは返さなくてよい」という認識で問題ありません。
“返して”と言いたくなるのはなぜ?その裏にある本当の気持ち
法律では“返さなくていい”とされていても、実際には「返して」と言ってくる人は少なくありません。そこには、いくつかの人間らしい心理が隠れています。
不満や執着があるから
関係が終わったという現実をすぐに受け入れられない人は少なくありません。
とくに、自分の意思に反して別れを告げられた側――いわゆる「振られた側」は、心の整理がつかず、相手をまだ引き止めたい、納得できないという感情を抱えたまま時間が過ぎていくことがあります。
そんなときに、「自分があげた物だけでも返してほしい」と感じるのは、ある意味で自然な反応です。
もう関係を取り戻すことができないなら、せめて“モノ”という形で何かを取り返したい。
それは、失った関係に対する不満や未練の表れであり、「何もかも失ったわけじゃない」と思いたい心の動きでもあるのです。
損をしたくないという感情から
「こんなにお金や時間をかけたのに…」という思いが頭をよぎると、人は自然と「その分を取り返したい」という気持ちになります。
たとえば、相手のために高価なプレゼントを買ったり、旅行や外食などにお金を使ってきたことを思い出すと、「自分ばかりが損をした」と感じてしまうのです。
そうなると、「あのプレゼントだけでも返してもらえたら気が済むのに」と考え始める人もいます。
これは、心理学でいう「損失回避」と呼ばれる心理状態で、「得をすることよりも、損をしないことを優先したい」という人間の本能的な反応です。
つまり、返還を求める行動の背景には、「あの関係がムダじゃなかったと思いたい」「自分の投資(時間・お金・気持ち)を少しでも取り戻したい」という、心のバランスを取ろうとする働きがあるとも言えるでしょう。
支配欲の現実化・復讐心の手段として
別れ際に感情がこじれてしまった場合、相手に対して怒りや恨みの気持ちを抱くことがあります。
そんなとき、「あれを返して」と言うのは、本当にその物が必要だからというよりも、相手を困らせたり、思い通りに動かしたいという気持ちから出てくることがあります。
たとえば、「プレゼントを返せ」と言えば、相手は戸惑ったり、気まずくなったりしますよね。
そうやって、相手の感情をかき乱すことで優位に立とうとする
それは、相手を支配したい・思い通りに動かしたいという「コントロール欲求」のあらわれでもあります。
つまり、返還要求がエスカレートする背景には、「物を通じて相手を振り回したい」「自分の怒りをぶつけたい」という思いが潜んでいることがあるのです。客観的に見るととても自分勝手な気持ちのようですが、本人もそのことに気づいていない場合が多いのが特徴です。
返してと言われたとき、どうすればいい?
相手から返還を求められたときの対応については、次のポイントを押さえておきましょう。
「これは贈与か、それとも貸し借りか?」まず確認するべきポイント
プレゼントや指輪を返してほしいと言われたとき、まず確認すべきなのは、それが本当に「贈与」だったのか、それとも「貸していただけ」だったのかという点です。
もし「君にあげるよ」と言ってプレゼントを渡したなら、それは法律的には「贈与」にあたります。
贈与とは、法律上「無償で相手に財産を与えること」(民法第549条)とされており、書面によらない贈与は、履行が完了した部分については撤回できません。つまり、一度渡したプレゼントを後から返せとは言えません(民法550条)
一方で、「あとで返してね」と明確に伝えられていた場合や、LINE・メールなどで貸し借りの証拠が残っている場合は、返す義務が生じる可能性があります。
このようなケースでは、「貸した」ことを主張する側がその証拠を示さなければなりません(「立証責任」といいます)。
つまり、まずはそのモノが「贈与」だったのか「貸与」だったのかを、自分の記憶と手元の記録をもとに冷静に整理することが、トラブルを防ぐ第一歩です。
もし判断に迷ったり、相手がしつこく迫ってくるような場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。
相手とのやり取りを記録しておくことも、後々の備えになります。
相手の感情を理解する
法的には返す必要のない物だったとしても、「返してほしい」と強く主張してくる相手に、正論だけで対応するのは逆効果になることがあります。
特に、別れたばかりの頃や相手が感情的になっているときは、冷静な話し合いができない状態である可能性が高いです。
たとえば、「これは贈与だから返す義務はありません」と突き放すように言ってしまうと、相手の怒りや執着をさらに刺激してしまい、状況が悪化することがあります。
中には、「こんなに冷たい対応をされるなんて許せない」と思い込み、逆上したり、しつこく連絡を取ってきたり、最悪ストーカー化するケースもあります。
ですから、法的な正しさだけを押し出すよりも、まずは相手の感情を刺激しないことに心を砕きましょう。
「この人は今、気持ちの整理ができていないんだな」
「自分を否定されたように感じて、取り乱しているのかもしれない」
そういう視点で相手を見ると、少し余裕をもって対応することができるようになります。
場合によっては、少し時間を置いて冷却期間をつくる、あるいは第三者を挟んで話すといった選択肢も検討できます。
感情が落ち着いたタイミングであれば、相手も冷静に話を聞けるようになり、無用な対立を避けられる可能性が高まります。とにかく、早期解決を目指すあまりに、自分の感情や考えをストレートにぶつけてしまうことはやめましょう。
あえて返すという選択肢もある
相手が異常なほどに「返還」に執着していたり、別れたあとも頻繁に連絡を取ってきたりするような場合は、法的に返す必要がないとしても、あえて物を返すという選択肢を取る方が安全で穏便に済むことがあります。
たとえば
- 「何度もLINEや電話で“あれ返して”と連絡がくる」
- 「返さないと家に来る、会社に電話する、などと脅してくる」
- 「SNSで嫌味や悪口を書かれている」
- 「一度断ったのに、何度もプレゼントの話を蒸し返してくる」
こうした行動は、すでに軽度なストーカー行為の予兆ともいえます。
その場合、モノの価値や自分の正当性よりも、自分の身の安全や心の平穏を守ることのほうが大切です。
実際、「高価なアクセサリーを返したらピタッと連絡が止んだ」「時計を送り返してからは粘着されなくなった」というケースも多く見られます。
物の返還を“勝ち負け”でとらえるのではなく、「これ以上関わらないための手切れ金」と考えると、気持ちも少し整理しやすくなります。
もちろん、「返したくない」と感じる気持ちも自然なものです。
ただ、相手の言動に不安を感じたり、「もし逆上されたら」と思うような状況なら、一時的に相手の言いなりになった感じがしても、長い目で見れば自分を守る賢い選択になることもあります。
どうしても対応に困るときは、警察への相談や、法律の専門家・支援団体などに早めに相談することも視野に入れてください。
まとめ
別れ際に「返して」と言われたプレゼントや指輪。
法律的には、贈与された物は原則として返す義務がありません。ですが、相手がそう言ってくる背景には、怒りや悲しみ、損をしたくないという思いなど、さまざまな感情が絡んでいることがあります。
その感情に火をつけず、トラブルを避けながら自分を守るためには、正論だけで押し返すのではなく、相手の心理と状況を冷静に見極めた対応が求められます。
「返す」「返さない」の判断は、法律だけでなく、あなたの安全や心の平穏を守る視点からも考えるべきです。
もし対応に迷ったときや、不安を感じるような相手の場合は、早めに専門家に相談することが、あなたを守る一番の方法になるでしょう。
小川たけひろ行政書士事務所では、離婚の悩みが少しでも軽くなるサポートを行っています。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付