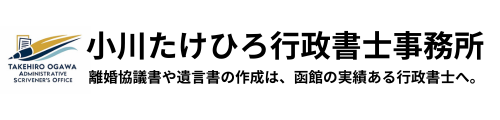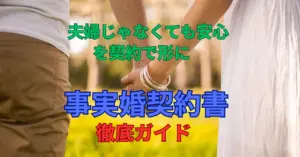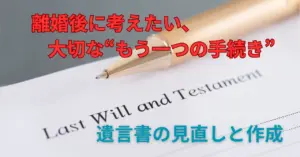離婚後もペットと暮らすには?共同飼育の注意点

「離婚しても、うちの子(ペット)とは離れたくない。」
一緒に暮らしてきた犬や猫は、ただの動物ではなく、かけがえのない“家族”です。
忙しい毎日の中で、癒しや喜びをくれた存在。時には、言葉にできない孤独や悲しみを受け止めてくれる相手でもありました。
だからこそ、離婚を機にその大切な存在と引き離されるという現実は、とてもつらいものです。
最近では、「どちらかが引き取る」という従来の考え方だけでなく、「離婚後も元夫婦で協力しながら飼育していきたい」と希望される方も増えてきました。
いわゆる“共同飼育”という形です。
しかし、この選択肢は思っている以上にハードルが高く、感情だけで進めてしまうと、思わぬトラブルを引き起こすこともあります。
本記事では、実際にご相談を受けてきた経験をもとに、共同飼育の実情や注意点、トラブルを避けるための対策について、わかりやすくお伝えします。
共同飼育って、そもそも可能?
まず知っていただきたいのは、法律上の前提です。
日本の民法では、ペットは“物”として扱われており、人間の子どものように親権や監護権といった制度は存在しません。
そのため、離婚時の話し合いではペットも財産分与の対象となり、基本的には「どちらが所有するか」を決めることになります。つまり、法律的には「二人で飼い続ける」ための明確な枠組みはないのが実情です。
とはいえ、当事者同士で十分に話し合い、合意することができれば、共同飼育というスタイルをとること自体は不可能ではありません。
たとえば、こんな方法があります
- 週ごと、月ごとに交代で預かるローテーション制
- 一方の住まいを拠点にし、もう一方が定期的に通ってお世話する
- 飼育費・医療費を分担し、互いに写真や動画を共有する
柔軟な取り決めができれば、ペットとのつながりを保ちながら生活することも可能です。
ただし、このスタイルがうまくいくかどうかは、元夫婦の「信頼関係」に大きく左右されます。
どちらかが無理をしていたり、ルールを守らなくなった時点で、共同飼育という形態は簡単に崩れてしまいます。
「かわいい」だけでは続かない。ペットとの生活にかかるお金
「お互いが協力すれば、何とかなると思っていた。」そんな声を聞くことも少なくありません。
その原因の多くが、「費用の負担」に関するすれ違いです。
たとえば、一般的な小型犬1匹を飼う場合、年間にかかる費用は以下のようになります
| 項目 | 年間費用の目安 |
|---|---|
| フード・日用品 | 約10〜18万円 |
| ワクチン・予防薬 | 約1〜2万円 |
| 医療費 | 約3〜10万円以上(状態により大きく変動) |
さらに、シニア期に入ったペットは、通院や手術などで医療費が高額になるケースも多く、10万円、20万円といった出費が突然発生することもあります。
このような負担について明確なルールがないままスタートすると、「どちらが多く支払っているか」「治療の判断に納得できない」といった不満が噴き出し、関係が悪化してしまうのです。
「ペット飼育合意書」で、トラブルを防ぐ
そうした事態を防ぐためにおすすめしているのが「飼育合意書」の作成です。
これは、お互いがどんな取り決めをしたのかを明文化して残すもので、万が一トラブルになった際の“よりどころ”にもなります。
たとえば、以下のような内容を盛り込むことができます。
- ペットの主たる飼育者とその住所
- 医療費や日用品の費用分担の割合
- 緊急時(入院・災害など)の対応方法
- 面会の頻度や方法(直接会う/写真・動画など)
- どちらかが飼えなくなった場合の引き取りのルール
- 死亡時の葬儀・供養に関する方針や費用負担
とくに毎月ある程度の額の金銭のやり取りがある場合は、公正証書にしておくことで、支払いが滞った際に法的手段を講じることもできます。
「ペットのことでそこまで大げさに…」と感じる方もいますが、いざ問題が起きたときに書面の有無が“心の余裕”を大きく左右します。
離婚後にペットと“会う”ための取り決めを詳細については、下記の記事をご参照ください。
離婚でペットと別れる…でも会いたい!面会の取り決め方法とポイント
離婚でペットと別れる…でも会いたい!面会の取り決め方法とポイント ペットは家族同然の存在。しかし、離婚時にどちらが引き取るかで争いになるケースは少なくありません。そして、ペットを手放さざるを得なかった側にとって「もう二度 […]
共同飼育に潜む5つの落とし穴
理想としては魅力的に見える“共同飼育”ですが、現実にはさまざまな困難もあります。以下に、実際に寄せられたご相談や事例をもとにした5つの注意点をご紹介します。
1. 関係が断ち切れず、感情的に消耗する
「もう元夫とは関わりたくない。でも、犬には会いたい」
そうした複雑な思いを抱えたまま関係が続くと、心が疲れてしまいます。
ペットとの再会は嬉しくても、それに伴って過去の感情がよみがえり、新しい生活に集中できないという方もいらっしゃいます。
2. 費用をめぐるトラブルが発生しやすい
「折半のはずが、自分の負担ばかり多い」
「勝手に高額な治療を受けさせて、あとから半分払ってと言われた」
こうした金銭面のすれ違いは、初めにルールを明確にしていなかったことが原因です。
3. ペットにもストレスがかかる
頻繁な環境の変化は、ペットにとっても大きな負担になります。
とくに猫は「人」より「場所」に馴染む生き物。住まいの行き来は体調や精神状態に悪影響を及ぼすこともあります。
4. 再婚や新たな生活に影響する可能性
新しいパートナーに、「元配偶者と頻繁に連絡を取っている」と思われることは少なくありません。
せっかく築こうとする新しい信頼関係が、過去とのつながりが原因で揺らいでしまうこともあります。
5. 法的拘束力に限界がある
たとえ合意書があっても、「会わせてもらえない」「育て方に納得できない」といった問題は、法律だけでは解決しきれません。金銭の支払いは法的手段で対応可能ですが、感情的な摩擦まではカバーしきれないのが実情です。
まとめ
「離婚してもペットとはできるだけ関わり続けたい。」
「ペットともう二度と会えないなんて耐えられない。」
こうした気持ちは、長い間家族として一緒に暮らしてきた方からしたら当然の感情です。
けれど、共同飼育という選択には、感情だけでは乗り越えられない現実がたくさんあります。
「ペットにとって、この暮らしは本当に幸せだろうか?」
「自分のこれからの人生に、どんな影響があるだろうか?」
そんな問いを心に置きながら、冷静に判断していくことが、結果としてペットにとっても、自分自身にとっても“ベストな選択”につながります。
小川たけひろ行政書士事務所では、ペットに関する共同飼育のご相談を多数受けてきました。
ご事情に寄り添いながら、現実に即した文書作成をお手伝いしています。
- ペット飼育合意書の作成
- 離婚協議書に飼育内容を盛り込むアドバイス
- 公正証書の作成サポート
など、柔軟に対応しております。
ペットの幸せも、自分の人生の再出発も、どちらも大切にしたい。
そう考えている方こそ、どうぞお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付