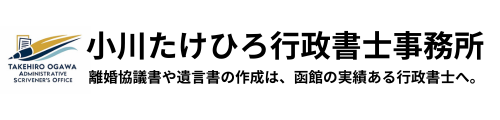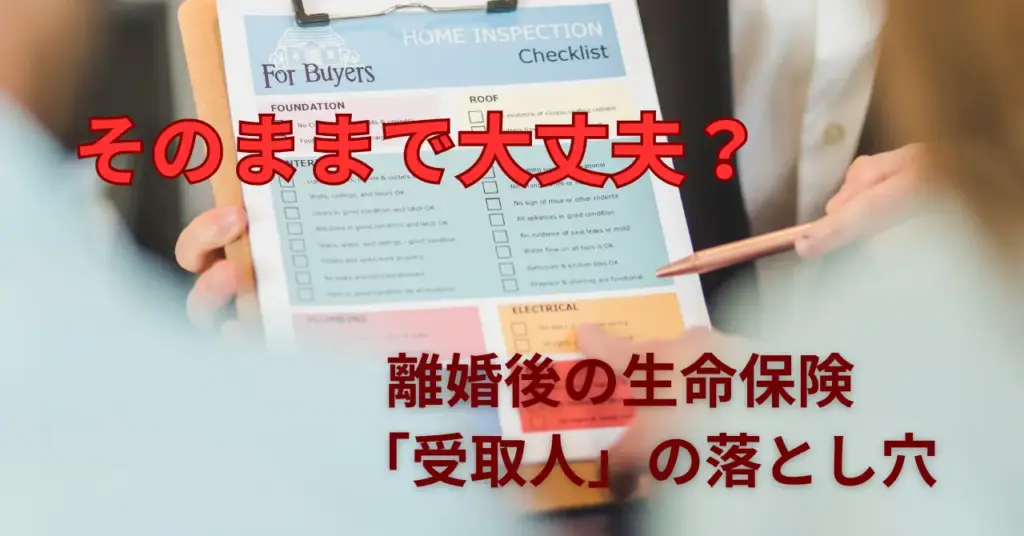離婚と同時に考えたい「遺言書」の話 ―離婚後を安心して暮らすために―
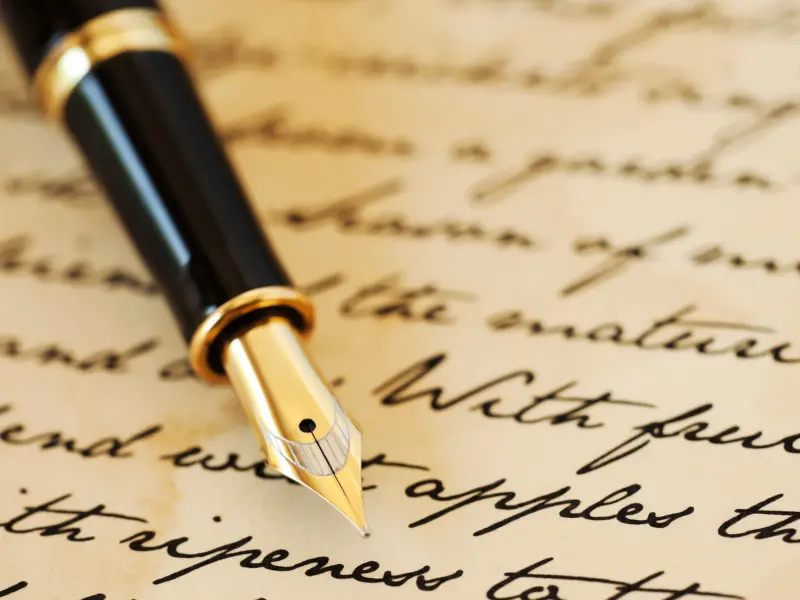
離婚が決まると、住まいの移動や名字の変更、財産分与、子どもの養育費の取り決めなど、短期間でさまざまな手続きが必要になります。
生活を立て直すだけでも手いっぱいの中で、一方で見落とされがちなのが、「遺言書の見直しと作成」です。
たとえば、離婚前に作成した遺言書をそのままにしておくと、意図せず元配偶者に財産が渡ってしまう可能性があります。
また、再婚相手や事実婚のパートナーなど、法定相続人でない人には、遺言書がなければ一円も財産を残すことができません。
この記事では、行政書士の視点から、離婚後に遺言書を見直すべき理由やタイミング、よくある誤解やトラブル事例、そして実際にどのように準備すればよいのかを、わかりやすく解説します。
【関連記事】
離婚後の生活設計を考えている方には、以下の記事もおすすめです。
離婚後、実家に戻る前に知っておきたい5つの注意点
離婚後、実家に戻る前に知っておきたい5つの注意点 離婚をきっかけに、「とりあえず実家に戻ろう」と考える方は少なくありません。 親との関係が良好であれば、住居や育児の面で大きな支えになることもあるでしょう。金銭的な負担が軽 […]
離婚後の生命保険、受取人の見直しをしないまま放置していませんか?
離婚後の生命保険、受取人の見直しをしないまま放置していませんか? 離婚後の手続きには、引越しや住民票の異動、銀行口座の変更、子どもの手続きなど、目の前のことで精一杯になるものです。 その中で、生命保険の"受取人"について […]
離婚しても「無効」にならない遺言書もある
「離婚したら、結婚中に書いた遺言書も無効になるんじゃないの?」このように思っている方もいらっしゃるかもしれません。確かに、民法の中には「相続させる意思がなかったと推測される場合には、その部分を撤回したとみなす」という規定があります。
民法1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
けれども、それには、相続させる意思がなかったと“推測できるかどうか”という前提が必要で、一律に無効になるわけではありません。
実際には、遺言者の意思がどうだったか、作成された当時の背景がどうだったかといった点が重視され、必ずしも「離婚=自動で撤回」にはならないのです。
そしてこれは、後々トラブルのもとにもなり得ます。
たとえば、あなたがかつて「配偶者にすべての財産を相続させる」と書いた遺言書が残っていて、そのまま離婚してしまったとします。何も手を加えなければ、その元配偶者に遺産が渡ってしまう可能性すらあるのです。
逆に、離婚後も相手に財産を残したいと考えている場合であっても、遺言書でしっかり意思を表しておかなければ、
「もう関係が切れているのに、どうして相続させる必要があるのか」と、他の相続人から反発が出ることもあり得ます。
「誰に、何を、どう残すか」を見つめ直す機会に
遺言書は、財産のことだけを決める書類ではありません。
実はそれ以上に大切なのは、あなたがこれまでどんな人生を歩んできたのか、そしてこれから誰を支えたいと思っているのかという“気持ち”の部分を表わすものです。
たとえば、こんな想いを抱えている方もいらっしゃいます。
- 離婚後も、子どもたちにはしっかり財産を残してあげたい
- 新しいパートナーと同居しているが、籍を入れていないので法定相続人になれない でも財産を残してあげたい
- 今は疎遠になったが、育ての親や長年世話になった友人に何か渡したい
こうした希望は、遺言書にきちんと記しておかなければ、法律上は何も反映されません。
再婚した場合も要注意です。
新しい家族に囲まれて過ごしていても、前の結婚での子どもが法定相続人として存在している限り、遺産は自動的にその子にも分配されることになります。
そのことに納得していれば問題ありませんが、もし「この人には多めに」「この人には気持ちだけで」などの思いがあるなら、遺言書でそのバランスを整えておくことが、後の争いを防ぐことにもつながります。
遺言書は「気持ち」と「現実」を整理するためのツールです
遺言書というと、「資産家や高齢者が使うもの」というイメージがあるかもしれません。
ですが、実際にはそれほど特別なものではありません。
財産の額にかかわらず、“誰に何を残すか”を自分で決めておきたい人には必要な手続きです。
特に、離婚や再婚を経験された方、子どもがいる方、法的には相続人にならない人に何かを残したい方は、早めに遺言書を作成しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
たとえば、次のようなケースです
- 子どもに「平等に分けたつもり」でも、書き方次第で不満や争いが起こる
- 内縁関係のパートナーに財産を残したいが、遺言がなければ1円も渡らない
- 特に面倒を見てくれた子や兄弟に多めに残したい
- 世話になった友人や団体に、少額でも感謝を伝えたい
- 思い出の品、ペットの世話、家の引き継ぎなど、お金以外のことも託したい
こういった内容は、話して伝えるだけでは不十分です。法律上の効力を持たせるには、遺言書としてきちんと形にしておくことが必要です。
財産が少なくても、書く意味はある
「自分には大した財産がないから、書く必要はない」と考える方もいますが、実際には金額の多さよりも“誰に何をどう渡すか”を明確にすることが大切です。
むしろ財産が多くない場合こそ、分け方で揉めないように配慮する必要があります。
遺産が少額だとしても、残された家族が「誰が何をもらうか」をめぐって関係が悪くなる例は決して珍しくありません。
また、遺言書に「どうしてこのように分けたのか」という理由やメッセージを一言添えておけば、納得や理解が得られやすくなり、感情的な衝突も防ぎやすくなります。
難しく考えなくて大丈夫
遺言書と聞くと、「難しそう」「特別な書き方があるのでは?」と思われるかもしれませんが、
内容が明確で、法的な形式を守っていれば、自筆でも書けますし、行政書士に相談すればより確実なかたちにできます。
書く内容も、堅苦しく考える必要はありません。
「この人に、これを渡したい」
「この人には、こうしてほしい」
そんな素直な思いが、書くきっかけになります。
遺言書は、死後のための書類ではなく、
“今の自分の意思を整理し、将来の不安を減らすためのツール”です。
家族のため、自分のために。
まだ先の話だからこそ、落ち着いて考えられる今のうちに、準備しておくことをおすすめします。
専門家に相談することで、安心が増す
遺言書は自分で書くこともできます。
でも、「形式を守れているか不安」「内容が法律的に有効か自信がない」など、気になることが出てくる方も多いはずです。
行政書士にご相談いただければ、
あなたの気持ちをきちんと汲み取りながら、法律に沿った形で遺言書を整えるお手伝いができます。
たとえば…
- 家族関係が複雑で、誰が相続人になるのか整理したい
- 相続で揉めないように、わかりやすく公平な内容にしたい
- 公正証書にするか、自筆証書にするか迷っている
といったお悩みも、一つずつ一緒に考えていきます。
遺言書は、“一人で黙々と作るもの”ではありません。
「もしものとき」に備えるために、“今”の安心をつくる作業でもあるのです。
行政書士ができること
行政書士は、あなたの人生やご家族の状況をじっくりと伺いながら、
法律にのっとった形式と、“あなたらしい想い”のバランスを取った遺言書づくりをサポートします。
具体的にはこんなことが可能です。
- 現在の家族関係を整理し、相続人や相続順位を正確に把握
- 財産の分け方について、もめにくい分配方法の提案
- 公正証書にするか、自筆証書にするかといった形式選びのアドバイス
- 言葉の表現や順序を整え、誤解や争いを避ける工夫
- 必要に応じて、公証人役場や他の専門家との連携
特に、「公正証書遺言を作成したいけれど、どう進めてよいかわからない」という方には、手続きの流れを一から丁寧にご案内することができます。
遺言書づくりは、一人で悩まず、誰かと一緒に
多くの方が、「遺言書は静かに自分だけで作るもの」と思われています。
でも実際は、誰かに相談しながら、“言葉にできない気持ち”を一緒に整理する時間でもあります。
家族には言いにくいことも、第三者である専門家には話しやすい。
そういったことも、相談を通じてたくさん生まれます。
- 「親との関係がうまくいっていないけど、相続はどうなる?」
- 「再婚して、前の子どもとの関係も気にしている」
- 「生前贈与した財産とのバランスも考えたい」
そんな複雑な想いや背景があるからこそ、一人で抱え込まず、信頼できる専門家と一緒に整理していくことで、“自分らしい遺言書”が生まれます。
遺言書の作成は、「もしものとき」に備えるだけでなく、「今」を安心して生きるための土台づくりでもあります。
だからこそ、思い立ったタイミングで、どうぞ気軽に専門家の力を借りてみてください。
まとめ
離婚という人生の大きな転機では、住まいや姓の変更、子どものことなど目の前の課題に目を奪われがちです。しかし実は、「遺言書の見直し・作成」もまた、非常に重要なステップです。
離婚によって“家族のかたち”が変われば、財産を託したい相手や伝えたい想いも変わるはず。特に、再婚相手や事実婚のパートナー、内縁関係の方、お世話になった方に財産や気持ちを届けたいと考えるなら、遺言書が欠かせません。
遺言書は、財産を「どう分けるか」だけでなく、「誰に、どんな想いを託すか」を整理するツールです。難しく考える必要はなく、あなたの今の気持ちを素直に書き出すところから始めてみてください。
行政書士などの専門家に相談すれば、法律的な不安を解消しながら、自分らしい遺言書を形にすることができます。離婚後の“新しい人生”を安心して歩むためにも、「今」のタイミングで一度、遺言書について考えてみてはいかがでしょうか。
小川たけひろ行政書士事務所では、離婚後の遺言書作成に関するご相談を承っております。「こんなこと相談していいのかな?」と思われることでも、どうぞお気軽にお声かけください。あなたのこれからを支える“ひとつの備え”として、丁寧にお手伝いさせていただきます。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付