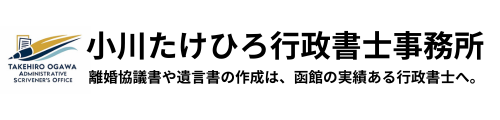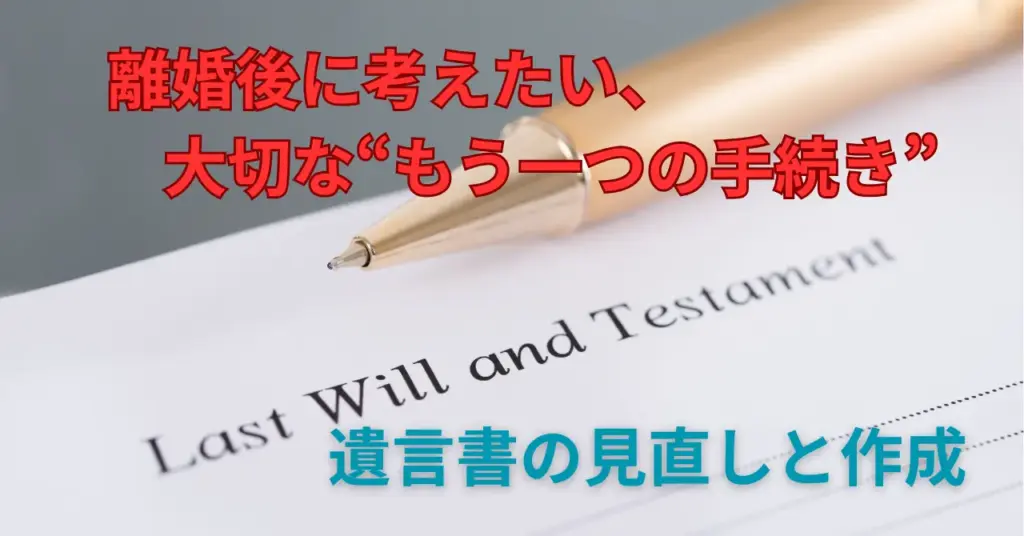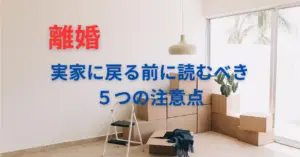離婚後の生命保険、受取人の見直しをしないまま放置していませんか?

離婚後の手続きには、引越しや住民票の異動、銀行口座の変更、子どもの手続きなど、目の前のことで精一杯になるものです。 その中で、生命保険の"受取人"について、見直しをしていないという方は少なくありません。
「保険のことなんて、正直あと回しにしてた」「なんとなく元配偶者のままになってるかも…」もしあなたがそういう状態なら、この記事はぜひ最後までお読みください。
特に問題なのは、元配偶者を受取人にしたまま放置し、その元配偶者がすでに亡くなっていたケースです。 気づかないうちに、生命保険の保険金がまったく想定していなかった第三者に支払われてしまうことがあるのです。
【関連記事】
離婚後の生活設計を考えている方には、以下の記事もおすすめです。
離婚後、実家に戻る前に知っておきたい5つの注意点
離婚後、実家に戻る前に知っておきたい5つの注意点 離婚をきっかけに、「とりあえず実家に戻ろう」と考える方は少なくありません。 親との関係が良好であれば、住居や育児の面で大きな支えになることもあるでしょう。金銭的な負担が軽 […]
離婚と同時に考えたい「遺言書」の話 ―離婚後を安心して暮らすために―
離婚と同時に考えたい「遺言書」の話 ―離婚後を安心して暮らすために― 離婚が決まると、住まいの移動や名字の変更、財産分与、子どもの養育費の取り決めなど、短期間でさまざまな手続きが必要になります。生活を立て直すだけでも手い […]
なぜ、生命保険の受取人を変更しなければならないのか?
生命保険は、契約時に「保険金の受取人」を指定します。多くの方は、配偶者や子ども、両親など、身近な家族を受取人に設定することが一般的です。これは、万が一のときに備えて、大切な人の生活を守りたいという思いが反映されたものです。
しかし、離婚を経験すると家族構成が大きく変わり、当初の受取人の設定が“今の自分の意思と合っていない状態”になっていることが珍しくありません。そのまま見直しをしなければ、保険金が想定していない人物に渡るという結果を招く可能性があるのです。
特に注意が必要なのは、受取人として設定されていた元配偶者がすでに亡くなっていたケースです。保険契約上の受取人が死亡していたことに気づかずに放置していた場合、万が一の際には、その元配偶者の相続人(たとえば親や兄弟姉妹、再婚相手の子など)に保険金が支払われてしまう可能性があります。
つまり、「自分が将来のためにコツコツと積み立ててきたお金」が、まったく関わりのない第三者に支払われてしまう可能性があるのです。たとえば、すでに縁が切れた元配偶者の親や兄弟姉妹、再婚相手の子ども、あるいはその配偶者の両親など、まったく面識のない人物に数千万円から数百万円という保険金が流れてしまうこともあります。
このような状況は、単なるうっかりや思い違いでは済まされない重大な問題です。本来、生命保険は自分の死後に備えて、愛する家族や支えてくれた人に感謝や安心を形にして届ける手段として機能するはずのものです。それにもかかわらず、受取人の見直しを怠ったことで、全く意図しない第三者に保険金が支払われ、残された家族が一銭も受け取れなかったという事態が発生する可能性があります。
たとえば、すでに交流のない元配偶者の兄弟姉妹や再婚相手の家族に保険金が渡り、本来助けたかった自分の親や子どもが何の支援も受けられない――そんな結果になってしまうのです。また、これを知った家族は、精神的にも大きなショックを受け、深い喪失感や不信感を抱えることになってしまうかもしれません。
つまり、この問題は放置しておくと、経済的にも心理的にも重大なダメージを残された家族に与えることになりかねないのです。
遺言では受取人を変更できない
「それなら遺言で『保険金は娘に』などと書いておけばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、残念ながら生命保険の受取人は遺言で変更することができません。
生命保険は、契約時に受取人を明確に指定することで成立する契約です。契約内容に基づいて効力が発生するため、後から書いた遺言の内容が反映されることは基本的にありません。つまり、遺言で「この人に渡してほしい」と意思表示をしても、保険会社は契約時に登録された受取人に従って手続きを進めるのです。
また、生命保険の保険金は民法上の「相続財産」ではなく、「みなし相続財産」と呼ばれる特別な性質を持ちます。これは、相続の対象とは別に、契約時点での指定に基づいて支払われるため、相続人同士で分け合う遺産とは扱いが異なります。したがって、たとえ遺言で他の人に保険金を渡したいと書いてあっても、保険会社にはそれを強制する力はないのです。
そのため、もしあなたが「保険金はこの人に確実に渡したい」と考えているのであれば、遺言に記すだけで安心せず、必ず保険会社に連絡をし、正式な手続きを通じて受取人を変更しておく必要があります。これを怠ると、自分の意思とは異なる相手に保険金が支払われることになりかねません。
税金面で大きな差が出てしまう
生命保険の保険金には、相続税の負担を軽減するための特別な非課税制度があります。
たとえば、保険金の受取人が配偶者や子どもなどの法定相続人である場合には、「500万円 × 法定相続人の人数」までの金額が相続税の非課税枠として認められるのです。
【事例】
亡くなった方に配偶者と子ども2人がいた場合、法定相続人は3人。
したがって、「500万円 × 3人=1,500万円」までの生命保険金が非課税となります。受取金額が1,500万円以内であれば、相続税は発生しません。
この制度は、家族を失ったあとも残された人たちの生活を支える目的で設けられています。
たとえば、保険金は葬儀費用や当面の生活費として活用されることが多く、相続直後の収入減少にも備える大切な資金となります。税金がかからず受け取れるという点は、精神的にも経済的にも大きな助けになるでしょう。
ここで重要なのは、非課税枠の適用には「受取人が法定相続人であること」が条件であるという点です。
つまり、誰を受取人に指定するかによって、最終的に課税される相続税の金額が大きく変わる可能性があるのです。
法定相続人以外を受取人にするとどうなる?
もし保険金の受取人を友人や元配偶者など、法定相続人以外の第三者に指定していた場合には、この非課税枠は一切適用されません。
さらに、相続税法上、「配偶者や一親等の血族(子や親など)以外」が保険金を受け取ると、相続税に20%の加算課税されるという決まりがあります。
たとえば、1,000万円の保険金を元配偶者が受け取った場合、本来よりも多い相続税を支払う必要があり、実際に手元に残る金額は大きく目減りしてしまいます。
元配偶者を受取人にしたままだと…
離婚後も「感謝や思いやりの気持ちから、元配偶者に保険金を遺したい」と考える方も少なくありません。しかしそのままにしておくと、相続税の非課税枠が使えず、さらに20%の加算課税までかかってしまうため、結果として思いが十分に届かない可能性があるのです。
せっかくの気持ちで遺した保険金が、税負担によって削られてしまえば本末転倒です。
だからこそ、「誰に保険金を渡すか」は、感情や関係性だけでなく、税の視点からも慎重に判断する必要があります。
生命保険は「残された人を守る制度」であり、同時に人生の最後に遺せる「思い」と「資産」です。
受取人の設定は、単なる名前の登録ではなく、税金や生活設計にも関わる重要な手続きです。
ご自身の意思をきちんと届けるためにも、税制上の影響を理解し、定期的な見直しを行うことが、安心を遺す第一歩となります。
受取人変更の手続き方法
保険の種類や契約している保険会社によって、手続きの詳細には違いがありますが、受取人の変更手続きは一般的には次のような流れで行われます。
- 保険会社のカスタマーセンターや担当窓口に連絡し、受取人変更届などの必要書類を取り寄せます。最近では、インターネット上から申請用紙をダウンロードできる会社も増えてきました。
- 契約者本人が書類に必要事項を記入し、署名・押印を行います。場合によっては、実印の押印が求められることもあります。
- 記入済みの書類と併せて、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を添付し、保険会社の指定先に郵送します。会社によっては、コピーのほかに住民票の提出が必要なケースもあります。
- 書類を受け取った保険会社が内容を確認し、問題がなければ正式に変更が反映されます。
通常、書類に不備がなければ、申請から完了までにかかる期間は1〜2週間程度です。ただし、提出内容に不備がある場合や繁忙期には、さらに時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
また、契約内容によっては、受取人の変更にあたって被保険者の同意が必要になる場合があります。ご自身の契約条件を事前に確認し、必要に応じて専門家に相談するのも安心です。
見直しのタイミングは「今」
「受取人を変えた記憶がない」「もしかしたら、昔のままかもしれない」と少しでも心当たりがある方は、今すぐにでも保険証券を確認してみてください。
たとえ現在もその相手が健在であっても、当時とは関係性が変わっている可能性があります。今の自分が大切にしたい人や、将来に備えて守りたい相手は、本当にその人なのかどうかを一度立ち止まって考えてみることが大切です。
繰り返しになりますが、もし受取人に指定していた方が元配偶者で、すでに亡くなっていた場合、保険金はまったく想定していなかった第三者――たとえば元配偶者の再婚相手の子や、元配偶者の親や兄弟姉妹などに渡ってしまうことがあります。その結果、本当にお金を渡したかった家族や身近な人には届かず、関係のない人が保険金を受け取るという、不本意な結果になってしまう可能性があります。
こうしたリスクを防ぐためには、生命保険の契約内容を定期的に見直すことがとても大切です。「今は忙しいからあとで」と思っていても、いざというときは突然訪れます。誰に保険金を届けたいのか、そのために何をしておくべきか――それを考え、行動に移すなら、まさに今がそのタイミングです。
行政書士にできること
行政書士は保険契約そのものを取り扱うことはできませんが、保険に関連する法的な書類作成や意思表示の整理において、さまざまなサポートを提供することが可能です。
- 離婚協議書に、生命保険の受取人に関する取り決めを明記することで、のちのトラブルを防ぐ
- 遺言書の作成を通じて、誰に何を遺したいかを明文化し、他の財産とのバランスを考慮しながら整理する
- 保険の受取人を変更したあとの経緯や合意内容を証拠として残しておくための文書作成や通知書の作成を行う
さらに、家族構成や相続関係に応じて、将来的に起こり得る争いを未然に防ぐためのアドバイスも可能です。ご本人の意思を正しく伝えるためには、第三者が見てもわかるような形に整えておくことが非常に重要です。
万が一のとき、大切な人が困らないように、そしてあなたの想いが正しく届くように――行政書士はそのお手伝いができます。一度、現状の整理と今後の備えについて、行政書士に相談してみることをおすすめします。
まとめ
離婚をきっかけに生活環境が大きく変わる中で、生命保険の受取人を見直すことは、どうしても後回しになってしまいがちです。引越しや各種名義変更、子どもの手続きなど、やるべきことが山積みで、保険の契約内容まで気が回らないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、そのまま何年も見直さずに放置していると、思いがけない第三者に多額の保険金が渡ってしまうという事態が起こる可能性があります。たとえば、離婚後も元配偶者を受取人にしていた場合、その元配偶者がすでに亡くなっていたとすると、保険金は元配偶者の家族など、まったく想定していなかった人物に支払われる可能性もあるのです。
保険金は、あなたの人生の中で「最後に誰かに遺せるお金」であり、遺された人にとっては生活を立て直すための大きな支えとなる重要な資産です。だからこそ、「誰に、どれだけの金額を託すのか」は、非常に大切な問題となります。
定期的に契約内容を見直すことは、ご自身の大切な想いを正しく届けるための第一歩です。今一度、ご自身の保険証券を確認し、必要があれば受取人の変更手続きを行いましょう。それは、大切な人に想いを残すための、かけがえのない準備になります。
「うちも保険を見直したほうがいいかもしれない」「どう手続きすればいいかわからない」という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。行政書士として、あなたの大切な想いが正しく届くよう、文書の整備や手続きをサポートいたします。
電話でのお問い合わせは、土日祝も対応可能(0138)56-0438営業時間9:00~19:00(定休日:土日祝)
メールでのお問い合わせ 24時間受付